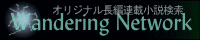第21話 交わる想い
|
悪鬼の中は、入った瞬間に気持ちの悪い寒気が全身に襲いかかってきた。 想像を絶する負の感情に当てられそうになるのをこらえるのに必死だった。 「清村……清村!!!」 名前を呼んでも返事はなかった。 目の前には長い長い螺旋状の大きな階段らしきものがあった。あとはただ、冷たい暗闇が広がるだけ。 俺は導かれるようにその階段を駆け上がっていく。 どれほど登ったか分からない。 だが、その終着点に清村はいた。 暗く、何も無い空間で膝を折って、蹲っている。 「清村!!」 清村に返事はない。 走り寄ってみると、清村は耳を塞いでずっと何かを呟いていた。 「いや、いや……お父さん……お母さん」 清村は両親を殺されたことが最もショックだったに違いない。 泣きながら、ずっと両親を呼んでいた。 「どうして……どうして、みんないなくなっちゃうの? 私が何か悪いことしたの?」 俺に問うたわけではないだろう。 けれど、清村の言葉は、俺の胸に割れたガラス片のように突き刺さる。 ぐすぐすと鼻をすすりながら、一度は声を小さくした清村だったが、すぐに頭を左右に振って叫ぶ。 「こんなことなら最初から一人でよかった!! その場だけの優しさなんていらないわよ!! 蘆屋くんたちとなんか友だちならなければよかった!!」 ざわざわと、胸が締め付けられるような、切りつけられるような感覚に俺は立ち尽くしていた。 最後に、泣き喚きながら清村は言った。 「何で好きになっちゃったのよ……こんなに苦しいのに、何で私はまだ影井さんが好きなのよ!! こんな気持ちいらない……いらない!!」 そうだ、俺は清村の気持ちを知っていた。 その気持ちを知っていながら知らん顔をしていたのだ。 けれどあまりにも無垢で無邪気な清村を見ていて我慢ができなくなった。 思わず口付けてしまった。 この気持ちはもう、止められそうにはなかった。 だからこそ、余計に俺は焦っていた。 茨木を確実に捕らえる陰陽師としての自分と、清村に惹かれ始めている男としての自分の間で迷っていた。 結局中途半端に清村を傷つけまいと突き放し、こんなにも傷つけた。挙句、茨木も自分ひとりでは捕らえられなかった。 俺は、なんと未熟な男なのだろうか。 清村をここまで追い詰めたのは俺だ。 心を砕いたのも、両親の死を防げなかったのも全て俺のせいだ。 ならば、俺が清村にしてやれることは一つだろう。 「清村……」 俺は清村を力いっぱい抱き締めた。 俺に触れて存在を認識した清村は、暴れ始めた。 「いや! 嫌だやめて!! もう影井さんなんかには騙されないんだから! 信じない!!」 「ああ、分かっている。どんな言葉をかけようとも、どんなにお前を本気で抱き締めようとも、もう信じてはもらえんだろう」 「分かってるなら放して!! もう私のことは放っておいて!!」 「放ってなどおけぬ! もう、俺はお前を二度と放したくはないのだ」 清村を抱きしめる手に、勝手に力がこもる。 もう、これ以上傷つけたくはない。 「嘘よ! 嘘!! 絶対嘘!! そうやって私を連れ戻したら、また突き放すんでしょう!? 影井さんはいつだってそう……私の気持ちをかき乱しておいて、最後は私をいつも置いていっちゃうじゃない……!!」 ああ、清村…… すまない、そんなになるまで俺はお前を追い詰めてしまったんだな。 俺なんかのために、こんなにも傷つけてしまったのだな。 「すまん。放すことはできん……だが、お前を無理に連れて帰ろうとも思わん」 「え……?」 清村は暴れるのをやめた。俺の言葉に耳を疑ったようだった。 俺は心に決めた決意を話す。 心を砕き、一人にしてしまった俺にできることは少ない。 もうこんなことしか、お前にしてやれない俺を許してくれ。 「共に冥府へ落ちよう。冥府は暗く冷たく寂しい、辛い場所だと聞く。そんな場所に、お前一人で行かせることは俺には耐えられん……だからせめて、共に行こう」 俺の本気を受け取ってくれたのかは分からない。 だが清村の目から、一筋の涙がこぼれた。 「清村、すまなかった。俺がしたことは許されることではない。分かってくれなくてもいい、だが知っておいて欲しい。俺がお前を大切に思って、傷つけとうなくてしてしまったことだということを……」 「影井……さん……」 清村の体の力が一気に抜けるのが分かった。 手をだらりと下におろし、俺に体を預けている。 「もう、自分の気持ちに嘘はつかぬ。俺はお前を失いとうない。愛しておる」 「嘘……」 「嘘で冥府になど一緒に行けるか、この馬鹿もの」 清村の目から次々と涙が零れ落ちる。 ひどい顔だ。 なのに、それすらも愛らしいと思えてしまうのだから、俺はよほど清村に惹かれているらしい。 「影井さ……ひっ……ひぅ……」 「もう泣くな。これからはずっと一緒におる。もう二度と約束を違えたりしないから、お前はどうか笑っていてくれ」 清村は俺の胸の中で小さく頷いた。 目の前の愛しい存在に、俺は静かに口付けた。 そうだ、俺は清村に惹かれてから、ずっとこの温もりを求めていた。 守りたかった。 「ありがと……影井さん」 やっと清村は笑ってくれた。 切なくて、無理に笑っているのはわかったが、泣き顔よりずっとよかった。 しかし、その笑顔を見た瞬間。 俺は清村に強く突き飛ばされた。 「みんなの声が聞こえる。影井さんの思いも今なら分かる気がする……」 まるでスロー再生の動画のようにゆっくりと、清村に手を伸ばしたまま俺は下に落ちていく。 「私、幸せだったんだね。こんなにもみんなに思われてたなんて……」 「清村! 清村ぁぁぁ!!!!!!」 「楽しかったです……ありがとう……ございました」 清村は小さく俺に手を振って、精一杯の笑顔を俺に向けた。 「ぐっ!!」 外に放り出された俺を見て、陵牙も蒐牙も、賀茂家の娘も声を上げた。 「影井様!! 清村さんは!!」 「なっなんや!? 悪鬼が!!」 「消える……!?」 見上げると、悪鬼は強烈な光を放って叫びを上げると、そのまま砂が風に飛ばされていくようにサラサラと形を失っていく。 これは、浄化……? 悪鬼として固まってしまった念を、清村が浄化しているというのか? 悪鬼が消え去った後、最後に残ったのは清村の姿だけだった。 中に浮いた状態の清村は、ゆっくり降りてきて、力を失ったように倒れた。 「清村!!」 「椿ちゃん!!」 「清村先輩!!」 「清村さん!!」 俺が清村を抱き起こすのも構わず、皆駆け寄って清村の安否を確かめる。 そして、蒐牙が青い顔をして言った。 「脈が……ない?」 「そんな……清村さん、冷たく……息もしていませんわ!!」 そこで、陵牙が唇を強く噛み締めて言った。 「命と引き換えに悪鬼を滅したんや……阿呆……!! なんつーことしてんねん!!」 「椿……もう目ぇ覚まさねぇってことかよ……!? 嘘だろ!?」 酒呑童子は地面を思い切り拳で殴った。 ずっとふざけるな、ふざけるなと腹の底から声をあげている。 「馬鹿な……清村! 目を開けろ!!」 どんなに揺さぶっても、清村は目を開けることはなかった。 青白い顔に、白い髪がかかっていて、まるで人形のようだった。 「清村……馬鹿者……何故一人で逝った……! もう二度と離れぬと、そう言ったであろう!!」 後悔しても、しきれない結果だ。 馬鹿な俺は、愛した女一人守れぬどころか、傷つけるだけ傷つけて死なせたのだ。 「何が才ある陰陽師だ……!! 陰陽師の力など、あったところで愛する女一人守れんではないか!!」 目を、熱いものが伝うのが分かる。 俺も、陵牙のことは言えん。 涙をこらえることすらできんなど、子供のとき以来だ。 「清村さん……」 そこで賀茂家の娘の表情が変わったのがわかった。 賀茂家の娘は手荷物の中から、古びた小瓶を取り出した。 中には強力な霊力の込められた水が満たされていた。 「影井様。これを……これを使ってくださいまし!」 「これは……なんだ?」 「御神水ですわ。賀茂家の人間が一生に一度与えられる、強力な霊力を持った水です」 「馬鹿な。お前、これがどれほどの価値のあるものか分かっておるのか? 一度使ってしまえば、二度と手に入れることはできんのだぞ?」 「構いません!!」 賀茂家の娘は俺に御神水を握らせて、鬼気迫る眼差しで言う。 「私はこんな水を失うことより、清村さんを失うほうがよほど嫌ですわ!」 俺はその言葉に、驚きを隠せなかった。 ずっと清村に嫌がらせをしてきたこの娘が、家宝とも呼べる御神水を差し出すと言うのだから。 しかし、その真剣な表情に偽りはないように感じた。 俺は頷いて御神水を受け取った。 そして、口を開く。 「俺の力では、この御神水の力を充分に引き出すことはできんだろう。お前たちも力を貸してくれるな?」 「当たり前やん!」 「もちろんです」 「元よりそのつもりですわ!」 皆が皆頷き、各々に印を切り始めた。 俺は御神水を清村にふりかけ、自らも印を切る。 「オンコロコロ、センダリ、マトウギ、ソワカ……オンコロコロ、センダリ、マトウギ、ソワカ」 皆、このときばかりは同じ呪文を一心に唱えている。 俺たちの家系は皆ばらばらで、力が交わるかはわからない。 だが、清村に戻ってほしいと思う気持ちが同じならば、必ず御神水の力は答えてくれるはずだ。 ふと、陵牙の体から白い光が放たれるのが分かった。 それだけではない、蒐牙の体からは灰色の光。 賀茂家の娘からは青い光が放たれた。 俺の体からも、微弱だが赤い光が漏れ出している。 「オンコロコロ、センダリ、マトウギ、ソワカ……オンコロコロ、センダリ、マトウギ、ソワカ……」 その光は空で一つの形となる。 大きな、赤い光を纏った鳥が、俺たちをいつの間にか見下ろしていた。 【我を呼び出したのはそなたらか?】 「あ……あなたは!?」 【我が名は朱雀。命を司りし者なり】 「朱雀!? まさか十二天将のか!?」 十二天将だと……あの、安部晴明が使役した最強の式神の……? しかし、もうその力を継承するものなどおらずに、何百年も呼び出したものはいないと聞く。 【強き願いに呼ばれて久方ぶりに目を覚ましたが……? そなたたちではないのか、我を呼んだのは】 「いえ、あなたをお呼びしたのは我らです」 俺は朱雀に跪き頭を垂れた。 この式神はとても俺が操れるような類のものではない。 礼を欠けば命を失う。 「お願いがあります。この娘をどうか助けてください」 【何故一度死した者を呼び戻そうとしておる? それは天命に背く行為であると分かっていて言うておるのか?】 「はい。ですが彼女は我々にとって必要な存在です」 【必要とな? それは何故だ?】 俺が答える前に、陵牙が声を張り上げた。 「椿ちゃんは俺らのダチだからです! 傷つけて、酷いことをしてしまったんに、命を懸けて俺らを守ってくれたんです」 「ええ。でも僕たちはそんな彼女に何ひとつしてあげられなかった……」 「彼女はそれでなくとも今まで辛いことに耐えてきた。これから幸せを知ってもバチは当たらないはずですわ!!」 必死の訴えだった。 それを、朱雀はじっと聞いている。 「俺は、彼女を幸せにしたい。もっと温かい日の下へ連れて行ってやりたいのです」 【日陰しか知らぬ哀れな娘に、お前たちは幸せを与えたいと願い我を呼び出したと? 死者に戻ってほしいと願うものなど星の数ほどおる。お前たちを特別扱いできると思うてか?】 「無理は重々承知しております。ですが我々の思いの強さは、あなたを呼び出せたことが証明していると思います」 朱雀はじっと俺を見据えている。 変な汗が出てくるのは、相手の力の強さ故だろう。 【よかろう。しかし、その娘の生き様から、そなたたちの思いが本物か、見せてもらうぞ】 朱雀は空へ舞い上がり、一度大きく羽ばたいた。 その羽が清村の体に吸い込まれていく。 【さぁ、直にその娘は目を覚ます。そなたたちがこれからその娘と共に生きる中で、その思いを示してもらおう。もし半端な思いで我を呼び出したとなれば、そなたらの命、永遠に責め苦の炎で焼いてやろうぞ】 朱雀はそう言うと、俺の体の中に入り込んできた。 燃えるような感覚が体を一瞬包み、右手の甲に痛みを感じた。 しかし、それ以降は何事もなく、何が起きたのかさっぱりわからなかった。 「う……うん?」 俺の腕の中でぐったりしていた清村が、うっすら目を開けたのはそれからすぐのことだ。 陵牙は感極まった不細工な顔で清村に飛びつき、顔面を殴られた。 蒐牙は呆れながらも、清村が起きたことに喜びを感じているようだった。 賀茂家の娘も、涙を流して清村の無事を喜んだ。 「な、なんですかこの状況……?」 「お前、分かっておらんのか?」 「え?」 一度死んだことすら理解していない、この阿呆面が今は妙に愛おしい。 俺は清村の頭から頬を撫で、最もふさわしい言葉を放った。 「皆、お前が好きだということだ」 その言葉に、清村の顔が今までにないほど笑顔になったのは、もちろん言うまでもない。 |