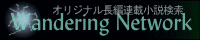第22話 日向に咲く椿
|
季節はもう、冬になっていた。 すっかり制服の下にセーターを着込んで、私は寒さに手をこすり合わせながら校舎を出た。 「椿ー!」 「あ、深散! 今帰り?」 「ええ、椿もですの?」 「うん」 深散は、あの事件の直後茶色のウェーブのかかった髪をばっさり切ってしまった。 理由を尋ねたら、志を新たにするため、気持ちを入れ替えるためだって言ってた。 「つーばーきーちゅわああああああああああん!!!」 「げっ……」 「うるさいのが来ましたわね……」 昇降口からすごい勢いで走ってきたのは、29代目蘆屋道満ことアッシー……蘆屋くんだ。 「ひどいわぁ!! 何で俺のこと置いてくんよぉ!」 「アッシーが私の仏頂面見て不愉快になるといけないと思って、さっさと帰らせていただきました」 「つ……椿ちゃん……もしかして、まだ根に持ってるん?」 「私は蛇のように執念深いのよ? あーあのときの胸の痛み、忘れたくても忘れられないわぁ……」 その言葉にアッシーは、よく漫画とかで見る縦線と青黒いオーラを纏いながらうな垂れた。 私は思わず噴出してアッシーの肩をぽんっと叩く。 「冗談よ、みんなが私のことを思ってしたことだって分かったんだし、もう怒ってないよ」 「ほんま!?」 「うん」 「ほんまにほんまのほんまのほんま!?」 「うるさいですわよ、蘆屋くん」 「な、なんやねんミッチー! そんな言い方せんでもええやん!!」 「気安くミッチーとか呼ばないでくださいまし!? しかも前の学校の6組の……えーっと宮元くんと同じ呼び名じゃないですの! かぶるとかホントありえませんわ!!」 「ミチルなんやからミッチーでええやん!! なんなら俺のことアッシーって呼んでもいいんやで〜?」 この二人、仲がいいのか悪いのか、打ち解けてからいつもこうなのよね。 私は自分を挟んで左右でギャーギャーと叫ぶ二人に半分呆れながら笑っていた。 「もぅ、椿! 蘆屋くんなんか放っておいて、一緒に帰りましょ!」 「なにぃ!? 椿ちゃんは俺と帰るんや!! お前は居残りして符でも書いてから帰り!」 「なんですってぇ!! 符くらい3分もあれば書けますわよ、馬鹿にしないでくださいな!!」 あー…… あーあーあーあーあーあー…… どうしよう、こうなるとこの二人止まらないのよねぇ…… 私はみんなに命を救われてからしばらくして、京都の学校へ転校した。 幸いこの学校は陰陽師協会の傘下の学校で、私が鬼斬の刃の扱いや、陰陽師の知識を学ぶのには不自由しない場所だった。 深散とはあいにく別のクラスになってしまったけれど、アッシーとは同じクラスになった。 まぁ知らない人だらけよりはよっぽどいいんだけど、同じクラスになったことでアッシーのテンションは前の学校の3倍増しだ。 深散は、この学校で陰陽師の心得の基礎を叩き込まれてる。 協会は今回の事件の罰として、深散から式鬼神を一式取り上げた。 きちんと気持ちを入れ替えたと協会が認めるまでは、大切な式鬼神の紅葉さんとは会えないんだそうだ。 早くて卒業までは、会えないだろうと深散は寂しそうに笑っていた。 あの事件は、深散にとっても辛いものだったはずなのに、陰陽師としてもう一度再スタートして、早く紅葉さんに会うんだと意気込んで、気丈にがんばり続けている。 一方のアッシーは、相変わらずバイトしながらふらふらしてて、家には寄り付いていないようだ。 アッシー曰く、少なくとも高校卒業まではこの生活はやめないとのこと。 理由を聞いたら、この先嫌でも29代目蘆屋道満として生きなきゃならないんだから、今のうちに蘆屋稜牙としての人生を謳歌したい、だって。 そう聞くと、アッシーは皆が言うほどうつけ当主じゃないんだと私は思った。 きっと蘆屋稜牙としての人生に悔いを残したくないんだろう。 だから、私は力の限り応援しようと思った。 そして私に関しては、茨木にお父さんとお母さんを殺されて、独りになってしまった私を、親戚は誰も引き取りたがらなかった。 まぁ、こんな見てくれの私をかわいがってくれたのは、母方のおじいちゃんくらいなものだし。 そのおじいちゃんももう亡くなってる。 こういうときは身内すら薄情なものだ。 財産に関しては奪い合いをしていたのに、私を引き取るという立場は押し付け合い。 私は正直そのやり取りにうんざりしていた。 でも、未成年の私を一人でいさせるわけにもいかないから、親戚たちは大いにもめていたのだ。 そんなとき、私を救ってくれたのは、意外な人物だった。 「ごめーん、二人とも。今日は先約があるんだ」 「え? そうなんですの?」 「そんなぁ、今日は椿ちゃんと一緒にめっちゃくちゃ美味いスイーツの店寄ろうかと思て調べて来たんにー!」 「蘆屋くんにスイーツとか……ぷっ」 「こらぁ! 今笑ったやろそこ!!」 「さぁどうかしらぁ」 はははは……なんていうか、こっちに引っ越してからずっとこんな感じで、めまぐるしい毎日です。 両親の死に関しては、鬼関係の事件だったから陰陽師協会が警察とリンクして全部面倒を見てくれた。 そうしてやっと落ち着きを取り戻して、今は両親がいない寂しさが消えたわけじゃないけれど、すごく満ち足りた毎日を過ごしてる。 今はいないけど、ここに蒐牙くんがいれば少しはマシなんだけどなぁ。 彼は今、調理師の免許を取るために必要な実務経験をつむために、釜飯屋さんのアルバイトに勤しんでる。 なんでも、 『蘆屋家の当主の栄養管理は僕自ら取り仕切ります。兄上の我儘を抑制できるのは僕だけですからね』 だそうな…… なんとも蒐牙くんらしい。 もちろん、アッシーは青い顔してとてつもなく嫌そうな顔してたけどね。 そういえば、両親のほかに、もう一人私の前からいなくなってしまった大切な存在がいる。 酒呑童子として覚醒した小鳩ちゃんは、私が命を救われた直後、姿を消してしまった。 今はどこで何をしているのかな…… もう、私たちの前には現れないのかな……? 正直、小鳩ちゃんはもっと話したいことあたくさんあった。 だから、いなくなってしまったことが実は結構ショックだったりする。 「まったく、やかましいのう」 「む、このじじくさくて嫌味な話し方は……」 「雅音さん!」 私は声の主の方に走り寄った。 特徴的なおかっぱ頭で、切れ長の目、薄く笑った口元。 そして、甘いコロンの匂い。 私の愛しい愛しい婚約者。 「遅いと思って来てみれば、椿をいつまでも引き止めておったのはお前らか」 「まっちゃん、来てたんか」 「今日は大事な用事があるのでな。悪いがお前らも付いてくるのはなしだ」 大学に戻った雅音さんは、もう卒論も書き終わって就活も別に必要がないから、意外に時間があるらしい。 だから、結構頻繁にこうして私を迎えに来てくれていた。 「分かってますわよ。影井様と椿のデート邪魔するほど、私たちも無粋じゃありませんわ。ね、アッシー?」 「せやなぁミッチー、しゃーないから今日はスイーツ食べに行くんお前で我慢したるわ」 「あらあら、じゃあご馳走になりますわね」 「誰がいつおごるっちゅーた!?」 そのやり取りに、雅音さんは深いため息をついた。 「うるさい奴らだのう」 「ふふっ、それを取っちゃうと二人のいいところの半分以上が吹っ飛びますからね」 「それは同感だ」 私は、雅音さんが京都へ帰る日が近づき、自分の現状を彼に話した。 親戚は財産に目がくらんではいるけど、誰一人私を引き取ろうとしないこと。 そうしたら突然雅音さんに手を引っ張られ、大きなジュエリーショップに連れていかれた。 そこで雅音さんは、私の指のサイズを測ったと思ったら宝石がキラキラ付いた指輪を選んでカードでほいっとその場で買ってしまった。 私は何がなんだか分からずに目を白黒させていることしかできない。 『椿、結婚するぞ』 そのとき、私は始めて雅音さんに下の名前を呼ばれた。 有無を言わせずに私は指輪を指にはめられて、呆然と雅音さんを見ていることしかできなかった。 『引き取り手がいないのなら、俺がお前をもらう。嫌か?』 もちろん、断れるわけもない。 ただ、いきなり結婚っていうのはさすがにちょっと戸惑った。 だって、付き合うっていう段階を通り越して結婚って、誰だってきっと戸惑もでしょ……? 『あ、あの……うれしいです。すごく。でも……私たちまだ、付き合ってもいませんよ?』 『む? そうだのう。いくら相思相愛とはいえ、いきなり結婚ではお前も戸惑うかもしれんのう』 『ごめんなさい……もちろん影井さんが嫌いとか、そういうんじゃないんです』 雅音さんはそのとき、私の鼻をつんっと指先でつついた。 『影井さんではない。雅音、だ』 多分、婚約を申し込んでいる相手に対して苗字で名前を呼ぶのは変だと言いたいんだろう。 だから、雅音さんも私を下の名前でそのとき呼んだんだと思う。 『結婚はお前が高校を卒業したその日にするとしよう。今は婚約にしておく。俺はお前を京都へ連れて行く、異論はないな?』 『はい……雅音さん』 こうして私は雅音さんの婚約を受け入れて、京都で暮らしてるわけだ。 結婚してるわけじゃないから、生活の面は不安だったけれど、鬼斬としての血を陰陽師協会の人たちは貴重と判断してくれたのか、学費も生活面もすべて支援してくれた。 さらには、両親のお墓も陰陽師協会が用意してくれた。だから、お父さんとお母さんは私の住む家の近くに眠ってる。 何から何まで協会の人たちにお世話になりっぱなしだけれど、おかげでつつましくも何不自由ない生活を送れていた。 何より、私には今大好きな婚約者と、大切な大切な親友たちがいる。 こんな生活に文句があるわけがない。 「まぁ賀茂は別に来ても構わんが……稜牙はうるさいし話がややこしくなりそうだからのう」 「なっ!? なんで俺だけ爪弾きやねん!?」 「うるさいからだ。賀茂、どうする?」 「いいえ。今日は遠慮しておきますわ。ここでアッシーを一人にすると、後がうるさそうですので、今日はこっちに付き合うことにします。どうせ、そちらにはいつでも行けますから」 「そうか、気を遣わせてすまんな」 アッシーは本当に泣きそうな顔で、深散は笑顔で私に手を振った。 私は雅音さんの車で、町を抜けてひっそりと佇む病院に連れてこられた。 「まだ、戸惑っておるか?」 「少しだけ……」 車のシートに腰掛けたまま、なかなかドアをあけられない私の手を、雅音さんは握ってくれた。 そしてぐっと胸に引き寄せてくれる。 雅音さんの胸の音が聞こえる。 コロンの甘い匂いも…… 「俺がそばにいる。何も怖いことはない、大丈夫だ」 「うん……」 私はしっかり雅音さんに手を引かれ、ある病室の前に立った。 その病室のプレートに記された名前は 『藤原星弥』 星弥は茨木に取り憑かれたことで、記憶に障害が出ているようだった。 そこで、陰陽師協会がある程度記憶が回復するまで、引き取り治療することにしたらしい。 星弥のところのおじさんもおばさんも、原因不明の記憶障害が治るのならばと、泣く泣くその提案を受け入れた。 私はずっと星弥に会うことを後回しにしていた。 もちろん、両親を殺したのは茨木であって、星弥じゃない。 星弥を責めたてる気持ちはない。 でも、複雑ではあった。 雅音さんは短くドアをノックする。 すると、すぐに返事があった。 「はーい? どうぞ」 部屋に入ると、見晴らしのいい個室の部屋になっていた。 そこのベッドで、退屈そうに、懐かしい顔が漫画を読んでいた。 「ああ、影井さん。こんにちは」 雅音さんは陰陽師協会の命令で、星弥の面倒をみていた。 星弥が家族旅行の際、たまたま私へのゆがんだ気持ちに悩んでいた星弥の気持ちを察知した茨木に付け入られ、茨木を持ち出してしまった件の責任を取らされているそうだ。 「調子はどうだ?」 「いやーホント体調は全然よくて、忘れてた記憶もちょっとずつ思い出してきてるんすけど……やっぱ数ヶ月前からの記憶は駄目みたいっす」 「そうか……」 私はその話をずっと雅音さんの後ろで俯いて聞いていた。 顔が上げられない。私の顔を見たら星弥は、私にどんな顔で話しかけてくるんだろうか? 「今日はお前に会わせたい人がいてな。連れて来た」 「へ?」 私はおずおずと前へ出て、顔を上げた。 星弥はきょとんとした顔で首を傾げた。 「誰?」 「え……?」 雅音さんは、小さくため息をついた。 「やはり、駄目か」 「雅音さん……?」 雅音さんは私の疑問にはその場で答えてはくれなかった。 「なに、彼女は俺の婚約者でな。美人だろう? 自慢しに来た」 「マジっすか!? へぇー……まだ若いってか、俺と同じくらいっすよね?」 「ああ、お前より一つ年上だな」 嘘……星弥が私の年齢を知らないはずない。 からかってるの? 「うおーやるじゃないっすか! めっちゃかわいいっすね!! ってか、影井さんとじゃ結構歳離れてますよね? 犯罪とか言われないように気をつけてくださいよー?」 「一発殴ったら記憶が戻るかもしれんのう」 「え!? いやいやいや!! それは勘弁!!」 そんな何気ない会話をして、時間は流れていった。 星弥は、茨木に取り憑かれる前の、無邪気でいい奴に戻っていた。 でも、その中から私と茨木に関する記憶は一切抜け落ちているようだった。 ある程度話が終わって私たちが部屋を出ようとすると、星弥は私と雅音さんを呼び止めた。 「影井さん、椿さん」 私たちは振り返り、ドアを開ける手を止める。 「お幸せに!」 私が頷くと、いたずらっぽく笑っていた星弥の目から突然大粒の涙がこぼれだした。 それは止まる気配を一切感じさせない。 「あっ……あれ?」 「星弥……」 「ははっ……なんでだろ? 涙とまんねー……」 私は星弥に駆け寄って、手を強く握った。 そして一言だけ、小さく言った。 「ありがと……星弥」 そのときばかりは私も、涙が止まらなかった。 星弥はなぜ私が泣くのか不思議そうだったけれど、二人ともしばらくの間泣くのをこらえることができなかった。 病院を後にして、雅音さんは海の見える公園に車を止めて、ベンチに私を座らせた。 そして近くの自販機からあったかいココアを買ってきてくれた。 海風がすっかり冷たくなっているから、気遣ってくれたんだろう。 「藤原星弥はな、鬼に手を出したことで大切なものを持っていかれたのだ」 「え……?」 「本来力のないものが鬼に手を出せば、あの程度では済まないはずなのだがな。あいつにもそれなりに鬼を扱う才能があったのかもしれん」 雅音さんが言っている意味がよく分からなかった。 「星弥の大切なものって……なに?」 「お前と過ごした記憶、いや……言うなればお前自身だな」 私は目を見開いた。 星弥にとって、私との時間はそれほど大切だったっていうの? 鬼に手を出した代償として持っていかれるほどに…… 「だが、どんなに記憶はお前を忘れても、心は……魂はお前を忘れておらんかったのだろう。その証拠があの涙だ」 「………」 私は言葉にならない気持ちでいっぱいだった。 「私、ひどい幼馴染ですね。何一つ、星弥の思いに気が付いてあげられなかったなんて……」 「………」 雅音さんは私の言葉を無言で聞いていた。 「あいつの気持ちを知っても、私は受け入れてあげることができなかった」 「本意でないのに、偽りでその気持ちを受け入れるほうがよほど残酷だ。気持ちを偽ることほどお互いのためにならないことはない。それは俺が身をもって体験したことだ。お前自身も、そうではないのか?」 そういえば、雅音さんは私のことを思いやるあまりに、偽りの気持ちで接して大きな後悔をしたって言ってた。 私も、本当は雅音さんと一緒にいたいと思っていたのに、言えずにいた。 それはとても苦しいことで、悲しいことで…… 胸が詰まりそうなことだった。 きっと、自分に嘘をついて星弥と付き合ったとしても、私たちは上手くいかなかっただろう。 だって、私は幼馴染としてしか星弥を見られていないのに、付き合ったりしたらお互い辛いだけだ。 「なにより、あの男を本気で思っている奴がいるからのう」 そうだ。 星弥を今も昔もずっとずっと思い続けている人が傍にいる。 自分の気持ちは受け入れられなくてもいいって切ない笑顔を浮かべながら、星弥の回復を願ってあしげなく病院に通っている深散の存在が、この誰も知り合いのいない京都での星弥の生活の心の支えになっているみたいだった。 「お前は、もう何も心配しなくてよいのだ。藤原星弥も、賀茂深散もきちんと自分の道を歩き始めた。もちろん稜牙も蒐牙もだ」 「雅音さん……」 「お前は俺だけ見ていればいい。両親の分も、俺がお前を愛してやる」 雅音さんが私をぐっと抱きしめる。 寒空の下なのにすごく、あったかい。 大好きな雅音さんの感触も、コロンの匂いも全部私を溶かしていく。 「もう、約束破ったら嫌ですよ?」 「ああ。分かっておる」 雅音さんと私の唇が重なりそうになったその瞬間だった。 「ひゅーひゅー! お熱いこったなぁ」 「なっ!? え……こ、小鳩ちゃん!?」 「……!!」 雅音さんの表情が険しくなった。 それはそうだ。 小鳩ちゃん……いや、今はもう式鬼神ではないから酒呑童子は、雅音さんとの式鬼神契約を無理矢理破棄したそうだ。 だから、もうあのかわいらしい小鳩ちゃんはどこにもいない。 それでなくとも、式鬼神契約を破棄した酒呑童子はふらっとどこかへ姿を消してしまったのだから。 「何をしに来た?」 「つれねぇなぁ? これでもついこの間までは主従関係だったのによぉ」 ベンチの前の手すりに腰掛けた小鳩ちゃんは、お酒を呑みながら笑った。 「その主従の関係を切ったのはお前だろう。よくも俺につき従うふりなんぞしてくれたな」 「なんだ? プライドが傷ついたか?」 「ふん」 酒呑童子はケタケタ笑って、ひょうたんを腰に戻して頬杖を付いた。 「まぁ、久々に式鬼神じゃなくなったんで、ふらっと日本を回ってみたが、やっぱり駄目だなぁ」 「なに?」 「恐れ、敬い、鬼を信じる人間はやっぱりこの時代にはほとんどいねぇ。豆まきが近づいたときの子供くれぇなもんだろ、鬼信じてるなんて」 呆れたように酒呑童子は大きなため息をついた。 「ってことで、俺の居場所はここかなと、思ったわけだ」 「また式鬼神のふりをするというのか?」 「ばぁか。おめぇみてーな偏屈野郎となんか、二度と契約するかっつーの」 影井さんはその言葉にムッとしているようだったけど、酒呑童子はそれを無視して私のほうを向いてニヤッと笑った。 なに、その笑顔? 「俺、椿と契約するわ」 え……? え………? えええええええええぇぇぇぇ!!!!!!? 「ま……待って待って!? 私陰陽師じゃないし!! 式鬼神の契約とか無理!!」 「だはは、わーってるよ。おめぇが式鬼神を操るなんざ不可能だ。だから契約は形式上、ってやつだな」 「な、なんで私なの?」 酒呑童子は「くくく」っと可笑しそうに笑って肩をすくめた。 「小鳩は、椿様が大好きだからですのよ」 何でだろう、小鳩ちゃん独特の口調をすごい野太い声で言われてるのに、それは彼の本心のように感じた。 雅音さんはやれやれとため息をついた。 「まったく。椿は俺の婚約者だ。手を出したらそれこそ茨木と並べて封印するからな」 「そらーごめんつかまつりたいな」 酒呑童子はんーっと伸びをするとゴキゴキと肩を鳴らした。 「んじゃぁ、いくぜ椿。おい雅音、手ぇ貸せ」 「ああ」 私の指から出た血で、札に大きく酒呑童子という名が記された。 そしてその札を雅音さんが酒呑童子の頭上に投げる。 酒呑童子という字が光を帯びて組み替えられ、小鳩と記された。 その瞬間、私たちの目の前から酒呑童子の姿は消えてしまった。 その代わり、空からひゅーっというかわいい音と共に、私の頭にぽすっと小さい小鳩ちゃんが札を持って落っこちてきた。 「ふぅ、契約完了ですの!」 「小鳩ちゃん!」 私は思わず久々に見る小さな小鳩ちゃんを抱きしめた。 「きゅー! 苦しいですのよ、椿様!」 「もう、小鳩ちゃん! 勝手にいなくならないでね!!」 「……はい。小鳩はずっと椿様にお仕えいたしますの」 うれしさに私がずっとぎゅーぎゅーと小鳩ちゃんを抱きしめていると、小鳩ちゃんの首根っこを引っつかんで私から引き剥がし、雅音さんは呆れたように私の頭に小鳩ちゃんを乗せた。 「小鳩は雄だ。あまりいちゃつくと仕置きをしなくてはならんぞ」 「あれ、雅音さん……妬いてる?」 「ばっ……鬼になんぞ妬くわけなかろう!!」 私は顔を真っ赤にしてそっぽを向く雅音さんが、妙にかわいく感じた。 「そっかー、じゃあ今日は小鳩ちゃんと一緒に寝ようかな」 そこで雅音さんはムッとした表情で、小鳩ちゃんの首根っこをまたつかんでぽいっとどこかへ投げてしまった。 小鳩ちゃんは「きゃーっ!」っと悲鳴を上げて近くの草むらに落下した。 それを見届けた雅音さんは、私を力いっぱい抱きしめてきた。 「ちょ、ちょっと雅音さん!」 「駄目だ。俺をあまり妬かせるな。他の男には人であろうと鬼であろうと触れさせとうない」 少し前の雅音さんなら考えられないほどに熱い言葉。 胸がドキンドキンと高鳴り続ける。 「……雅音さんったら。今までと全然違うのね」 「もう自分に嘘をつくのはやめたのだ」 雅音さんはどこから出したのか、真っ白な椿の花を一輪出してやさしく微笑んだ。 「これ……」 「覚えておるか? お前に初めてやった贈り物だ」 「うん……覚えてる」 そう、真っ白な私の名前と同じ花。 私はこれをもらったとき、素直にうれしかった。 そして、同じものを雅音さんはまた私に送ってくれた。 「もう、お前は日陰に咲く椿ではない。どうか俺の前で、美しく咲いていてくれ」 今度こそ、雅音さんと私の唇は重なり合った。 私は今までずっと日陰にいながらも両親という小さな木漏れ日に支えられて生きてきた。 でも、もうここは日陰じゃない。雅音さんや小鳩ちゃん、そして蘆屋くんや蒐牙くんや深散っていうかけがいのない太陽に照らされて生きている。 だから、きっとこれから辛いことや悲しいことがあっても一人で抱え込まずに生きていけるはず。 だって、私は大好きな大好きな雅音さんという太陽の傍で花を咲かせる幸せを知ることができたのだから。 |