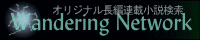第13話 安倍曇暗と源紅雪 其ノ三
|
運命、そんなものが存在するのか俺は考えたこともなかった。 だが、椿と出会って、椿のこと、そして鬼斬の娘について知るに連れて、それは存在するのではないかと思うようになった。 いや、運命などという言葉では片付けられない"宿命"というものなのかもしれない。 運命は文字通り運んで変えられる。 しかし宿命は……その身に、いや魂に宿ったサダメ。 逃れられないものだとすれば、俺はどうすればいい…… 鬼斬として生まれてしまった椿の宿命を、俺はどうしてやればいい? 土蜘蛛という、自らの祖先という名の同胞を斬る宿命。 そしてその土蜘蛛たちから、人々を守らねばならない宿命。 どれをとっても酷な話だ。 何故椿でなければならなかった? 何故椿が鬼斬の娘なのだ…… 「大変でございます紅雪様!!」 「一体どうしたのです? ややが驚くでしょう?」 子供を抱いた紅雪の元に血相を変えて使者がやってきたのは、まだ曇暗と紅雪の子供が乳飲み子のときだった。 新年が終わり、木々には白い雪が覆いかぶさっているような季節。 使者は、紅雪にとがめられても様子を変えることなく言った。 「都の鬼門の方角より、正体不明の軍勢が押しかけてきております」 「鬼門!? 一体どういうことですか?」 「分かりません。曇暗様は既に帝のところへお向かいになられました。紅雪様も急ぎお支度を!」 「……分かりました」 紅雪は幼い子供を乳母に預けて支度を始めた。 曇暗と結婚してから、紅雪は男の姿をすることがなくなった。 しかし、刀を握るとなればそうもいかない。 彼女は久々に戦に出る準備をしたのだった。 「流石に、産後では体がなまっていそうで不安ね」 髪を結いながら紅雪は鏡の前で苦笑いをした。 しかし、その顔はすぐに女の顔から一人の武士の顔に変わった。 「帝、召致に応じましてござ今する」 「おお、紅雪! 待っておったぞ」 紅雪は既にその場にいた自分の夫である曇暗の横に並んで座った。 少しばかりの懐かしい気持ちを抑え、彼女は顔を上げた。 「状況はどのように?」 「突如何の前触れもなく鬼門が開いた。そこから謎の輩たちが押し寄せておる」 「何の前触れもなく? 曇暗様の占いにも出ていなかったのですか?」 「ああ、本当に気配も予兆もなく、だ」 そのときの曇暗は、この脅威を予知できなかったことに少し動揺しているようだった。 紅雪は、そんな曇暗の分も自分が落ち着かなければならないと感じたのだろう。 「私と曇暗様を呼んだということは、その軍勢は生きた人間ではないということですね?」 「鬼門から押し寄せる軍勢。冥府からの進軍と考えて間違いあるまい」 天皇の言葉に紅雪は頷いた。 「分かりました。全力を持って京の都をお守りいたします。帝には指一本触れさせませぬ」 「産後だというのにすまぬな」 「いいえ、これが私の役目。先祖代々帝にお仕えしてきた私の使命でございます」 「紅雪……お前と曇暗には感謝しておる。誰もやりたがらないような仕事を、身を挺して率先してやってくれているのだから」 「帝、それはあなた様が私たちによくしてくださるからです。異形と忌嫌われた私たちを、普通の人々と同じように分け隔てなく接してくださった。私たちはそのお心に報いたいのです」 紅雪は刀を持って立ち上がった。 「帝、私は最前線に出て敵を討ち取りましょう。あなた様のことは必ずや曇暗様がお守りくださいます」 「何を言っておるのだ紅雪! 前線は危険だぞ!!」 「いいえ、危険だからこそ私が行くのです」 「紅雪……少し話がある、よいか?」 曇暗は天皇の反対を押し切ろうとする紅雪と共に天皇の前から席をはずした。 「どうしたのですか、曇暗様」 「今回ばかりは俺もお前が前線に出るのは反対だ」 「何故です?」 曇暗はふわりと二枚の符を取り出して言った。 「十二天将の六合と天空だ。この二人が言っておる、この戦でお前は確実に命を落とすと」 「え?」 「攻めてきているのは、かの昔、鬼斬に滅ぼされた土蜘蛛一族だそうだ」 「鬼斬に……滅ぼされた?」 紅雪は曇暗の言う言葉が理解できなかった。 「鬼斬はある土蜘蛛の姫君が同胞を斬ったことから始まった。そして今攻め込んできているのは鬼斬と帝を恨む土蜘蛛一族……狙いはお前と帝だ」 「ならば、ますますを持って私が前に出なくてはいけないのではありませんか?」 「紅雪!」 紅雪は先ほどとは打って変わって、全てを悟ったように言った。 「もしも私が敵の狙いであるのならば、その敵を全て打ち砕くまで。帝にその脅威が及ぶ前に、ね」 「しかし! 敵はお前一人で戦えるような数ではないぞ!!」 「私の背には、曇暗様がおります」 「!!」 その紅雪の顔は、曇暗を信じきったものだったという。 「いつだって二人で苦難を乗り越えたでありませんか。酒呑童子を倒したときも、茨木童子を倒したときもそう。百鬼夜行を相手にしたときだってありました。でも、私は怖くなどありませんでしたよ。だって私の背中を曇暗様が守ってくださっていたから」 「お前という奴は……」 曇暗は紅雪をきつく抱きしめた。 その体は小さく震えていたという。 「絶対に死ぬな紅雪……俺の占いは当たることで有名だ。こんな不吉な占いは当たってほしゅうない」 「曇暗様、運命とは変えていってなんぼでございますわ。大丈夫、私たちにはその力がきっと備わっています」 曇暗と紅雪はそっと口付けを交わした。 これが、最後の口付けになるとも知らずに。 「皆のもの! 相手は物の怪だ、油断するな!!」 「ははっ!!」 紅雪の指示の元、多くの兵たちが前線へと出て行った。 曇暗や他の宮中の陰陽師たちは、物の怪から天皇を守るべく結界を張る役回りとなったのだった。 「なんや、浮かない顔しとるのう曇暗」 「お前は……蘆屋のところの三代目か。流石に法師陰陽師だからどうこうとは、言っていられない状況のようだのう」 「ははっ、みたいやなぁ。俺見たいのが堂々と帝のお命守れるっちゅーことは、よっぽどやもん」 曇暗と年恰好の変わらない法師姿の陰陽師は、三代目蘆屋道満。 法師陰陽師を当時は忌嫌っていた貴族たちも、天皇の一大事と聞いてはそんなことを言っていられなかったのだろう。 「あらあら、これは凄腕の陰陽師が二人も顔を揃えて珍しい」 「ほう……貴女もいらしていたのか、賀茂家の姫君」 「姫君はおよしになってくださいまし。今ここには陰陽師としているのですから、そう扱っていただかなければ困りますわ」 「……そうであったな。貴女は今の賀茂家の中でも最も優秀な陰陽師。失礼した」 「くすっ、それでよろしくってよ。さぁ、ぼやぼやしていられませんわ。宮中にくまなく結界を張らなくては」 「ああ」 「任しとき」 宮中至る場所に陰陽師たちが招集され、帝を守る厳戒態勢となった。 一方、敵を迎え撃った紅雪は唖然としていた。 攻めてくる軍勢が人の形をしていなかったのだ。 黒いもやのようなものがまるで人のような形を取ってこちらに向かってきているだけ。 それはなんとも不気味な光景だっただろう。 「百鬼夜行のほうがまだ見た目に優しかったわね……この目をもってしても姿を確認できないなんて……」 鬼斬の娘の目には、元より異形の者たちがはっきり見える。 しかし、このときの黒い軍勢は全くといっていいほどその形を確認できなかったそうだ。 黒い軍勢は波のように紅雪たちの隊を襲った。 斬ることもできない相手に紅雪は目を瞑ったが、次の瞬間にはその黒い波は消えていた。 「なんなの……?」 戸惑う紅雪は次の瞬間、強烈な殺気を感じ、その場から飛びのいた。 「なっ!?」 紅雪が驚くのも無理はなかった。先ほどまで一緒に敵を迎え撃っていた武士が、紅雪に刀を向けていたのだ。 しかも一人や二人ではない。 多くの武士たちが紅雪に刀を向けていた。 思えば実体を持たない土蜘蛛たちの狙いはまず肉体を得ることだ。 紅雪は知らず知らずの間に敵に肉体を提供し、敵陣の真ん中に立っていたということになる。 「冗談……ではないようね」 紅雪は刀を抜いた。 「傷つけずに助けられるかしら……保証はないわね!」 紅雪のは一人、屈強な武士たち相手に戦った。 鬼や物の怪を普段より相手にしている紅雪にとって、彼らは取るに足らない相手のようにも思えたが、取り憑かれた相手は土蜘蛛。 太古より狩りに行き、今の人間よりも身体能力は高い相手だ。 紅雪が苦戦を強いられている間にも、宮中に向かって黒いもやは差し迫っていた。 「うわぁーあかんあかん、あの黒いやつこっちに迫ってきてんで!?」 「やはり、人一人にはあの軍勢は止められますまい」 「紅雪……」 黒いもやたちは、やはり生きた人間ではないために宮中の結果以内には入ることはできないようだった。 しかし、入れないのは"生きた人間"ではない黒いもやだけ。 「ぎゃあっ!?」 内裏のほうから叫び声が聞こえてきた。 見れば門番をしていた男が、もう一人の門番を切り捨てていた。 「なっ!? 何やってんねんあいつ!!」 「違う、よう見ろ!! あやつ、周囲に黒い妖気が見える……憑依されておるのだ!!」 「なんてこと!! あのもや、人魂ですの!?」 3人の陰陽師は一斉に声を張り上げた。 「よいか、あれに憑依されたものは結界を通過してくる!! 憑依した人魂を滅せよ!」 「気ぃ抜いたら殺されんで!!」 「帝に一歩も奴らを近づけてはなりませんわよ!!」 しかし、人魂は都の人々の体を乗っ取り、内裏に入り込もうとしていた。それこそ、宮中にいる陰陽師や武士たちではどうにもできないほどの数の憑依された人間たちが襲い掛かってくる。 今で言うゾンビに周囲を囲まれたような状態だろう。 「くっ!! 次から次へときりがない!!」 「陰陽師の中でもあんま力のない奴はどんどん憑依されとる……! 鬼道丸!! 絶対人間は殺すなよ!」 「結界内に入られては無意味……まったくやってくれますわ!! 紅葉! やっておしまいなさい!!」 このとき、三代目蘆屋道満も賀茂家の姫君も自分が従属させていた鬼を使い人々を弱らせ祓いをしていた。 しかし、緊急事態はそこで発生した。 「はーん? 鬼か、俺らの眷属が人間につき従ってるなんて情けねぇったらありゃしねぇ」 「もう少しで帝のところにつけるんだからさぁー、邪魔しないでよね!」 道満と賀茂の姫君の式鬼神は一瞬にして元の符に戻されてしまった。 まぁ、現代のように石にされなかっただけマシなのかもしれないが、それでも戦う手段が大幅に減ったことは間違いない。 「なんやねんあれ!? 鬼道丸が手も足も出ずに符に戻されたやて!?」 「私の紅葉が……一体どういうことですの!?」 「はっはっは! てめぇら帝の守護者か? こんな雑魚共が守ってるようじゃ、帝の命なんかあっという間にいただけるな」 「打猿、油断はしちゃ駄目だよ」 「わーってるって、国摩侶は心配性だなぁ」 記録によれば、陰陽師たちの前に立ちふさがったのは打猿と国摩侶という土蜘蛛だった。 現世でも奴らは俺たちの前に現れた。考えればよほど力の強い土蜘蛛だったのかもしれない。 「さぁて、こいつらもみてみりゃ俺らの血が混じってるな? どうする国摩侶、体乗り換えるか?」 「んー……僕はこれでいいよ。帝に付き従ってるような子孫の体には入りたくないしね」 「ははっ、ちげーねぇ。じゃあ殺っちまうかぁ!」 襲いくる土蜘蛛に、道満と賀茂の姫君は生身で立ち向かったという。 もちろん陰陽術を用いて自己の身体能力を上げていたのだろう。 「曇暗様! 早く帝のところへ!!」 「何を言っておる!!」 「何を言っておるはお前のほうや! お前が帝を守れる最後の砦やねんで!? 嫁はんかて前線で戦ってるんや、ほうけてる暇はないで!!」 「!!」 曇暗は前線で戦う紅雪のことを思うと、その場でためらっているわけには行かなかった。 「二人とも済まぬ!!」 曇暗は走った。 まだ帝の部屋に通じる廊下に異常はない。 どうやら打猿と国摩侶は先陣を切って攻めてきたようだった。 あの二人が何とか持ちこたえてくれればよし、そうでなくても自分が必ず帝を守る。 そう心に今一度誓いなおして曇暗は走ったのだった。 |