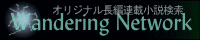第14話 安倍曇暗と源紅雪 其ノ四
|
曇暗が天皇の下へ駆けつけると、彼は目を見開いた。 ボロボロの服を着た女が、天皇にどこかから拾ってきた刀を向けていたのだから無理もない。 「やめろ!! 帝に危害を加えることは俺が許さん!!」 「ん? 貴様は我が眷属か。意外なことだ、速来津姫は我らを皆殺しにしたと思っていたが、これほどまでに眷属が増えているとはな。まぁ、おかげでことが運びやすくて助かるが」 「貴様何者だ……」 女は、ふっと笑うと曇暗を見据えていった。 「我は海松橿。かの昔、同属とそこの帝の祖先に打ち滅ぼされた、哀れな民の長。今ここで積年の恨みを晴らしてくれようぞ」 「させぬ……! 貴人、帝を守れ!! 大裳!! 敵を討て!!」 刀を振りかぶる海松橿姫に対し、曇暗は素早く式神を飛ばした。 海松橿姫の刃は大裳の槍によって跳ね除けられた。 「ほう、これは驚いた。貴様すばらしい力を持っているな」 「なに……?」 「くくく、感じるぞ、お前の中には我らの血が色濃く流れておる。才ある血と純粋な血が混じった最高の眷属だ」 「何を言っておるのだ貴様は……」 曇暗にはおよそ海松橿姫の言うことは分からなかったろう。 彼女は曇暗の父・晴明の土蜘蛛のシャーマン的な能力に才ある血と、母親の純粋な土蜘蛛の血に惹かれたのだろう。 「くくく、私に体を提供できることを光栄に思うがいい!!」 「!?」 *************************** 「!!!!!」 紅雪は、自分に襲い掛かってきた土蜘蛛たちを一掃して、内裏に向かっている最中だった。 彼女も土蜘蛛との戦いで酷く傷ついていたが、嫌な予感が隠せずに、傷ついた体に鞭打って、足を引きずりながら走っていた。 「くっ……もっときちんと動け!! 帝の危機に動かない足など、切り捨てるぞ!!」 紅雪はそう自分に言い聞かせながら必死に走り続けた。 宮中は酷い状況になっていた。 人々が傷つき、黒い人魂が飛び交っている。 「何ということ……」 「お前……曇暗のところの嫁か?」 「!」 紅雪は、柱にもたれかかって苦しそうにしている男を見た。 「貴殿は……三代目蘆屋道満殿か!?」 「ああ……情けない姿晒してしもて悪いなぁ」 「大丈夫なのですか!?」 「ん、ああ……でもちぃと頑張りすぎたわ……動かれへん」 見れば道満の腕は黒く焼け焦げており、今後もこれを治療する手立てはないのではないかというほどに酷い怪我をしていた。 「早く行き……曇暗が帝のところに行ったんやけど、さっきから嫌な気配がしとる。帝が危ないかもしれん」 「ですがそんな怪我のあなたを置いては!!」 「そこのヘタレの面倒は……私が見ますわ」 「!」 奥から、同じように酷く傷ついた賀茂の姫君が現れた。 「お二人とも傷だらけではありませんか……」 「俺らは大丈夫や……あんたの役目は帝を守ることやろ」 「そうですわ……早くお行きになって」 紅雪はぐっと唇を噛んで立ち上がった。 「二人とも……ご無事で!」 二人を残して紅雪は帝のいる部屋まで一目散に走った。 確かに異様な気配が先ほどから帝の部屋から取り巻いている。 「帝! ご無事で……!?」 「ん?」 紅雪は驚きを隠せずに目を見開いた。 自分の愛する曇暗が、共に天皇を守ると誓った曇暗が、帝の首を締め上げていたのだ。 「いかん……紅……雪……逃げろ!!」 「帝!!」 曇暗は突然天皇などどうでもよくなったかのように、彼をうち捨て地面に刺さっていた刀を抜き、紅雪に斬りかかってきた。 「曇暗様!? 一体どうしたというのですか!!」 「白い髪、赤い右目に青い左目……貴様、速来津姫の眷属だな!! 忌々しいその見てくれ、忘れはせんぞ!!」 「貴様……曇暗様ではないな!?」 しばらくは鍔迫り合いをしていた二人だったが、曇暗はこれでは勝負がつかないと感じたのか、距離をとった。 「くくく、貴様は知る由もないか。我が名は海松橿。貴様の祖先に滅ぼされし土蜘蛛の長だ」 「土蜘蛛の……長?」 「もう土蜘蛛という名も廃れたか。ならば貴様らの言葉で言い直してくれよう。我らは鬼と恐れられし存在の始祖だ。分かるか、鬼斬の娘」 「鬼……!!」 紅雪の中で、嫌な記憶が思い出された。 昔、曇暗が明かした自分の身の上の不安。 『のう紅雪。俺は自分がよう分からんのだ。半分鬼の血が混じっているのだとすれば、俺はいつか帝に仇なす存在になるやもしれん……あのお方はお優しい。俺の手で傷つけるなど、絶対にしとうない』 紅雪はぎゅっと胸を押さえた。 『鬼斬のお前が、俺を鬼と判断したのならば、今ここで切り捨ててはくれんか?』 曇暗は、こうなることを予測していたのだろうか。 絶対にこんな日は来ては欲しくない、そう彼女は思っていた。 しかし、目の前には鬼と化し、天皇に仇名す曇暗が立っている。 「曇暗様……」 紅雪はうつむき、ぐっと刀を捨てた。 「どういうつもりだ? くくく、そうかこの男はお前の夫だそうだな。殺せぬか? これはいい! 積年の恨み、こうも簡単に果たせるとは」 曇暗に取り憑いた海松橿姫は刀を再び振り上げ、紅雪に切りつけた。 しかし、その刀の刃は、鈍い金属音を立てて二つに折れてしまった。 「なっ!?」 「鬼斬の刃よ、我源紅雪の名の下に悪鬼を切り捨てる力となれ……」 紅雪は刀が折れて驚いている海松橿姫を突き飛ばし、そのまま馬乗りになった。 手には真っ赤な刀身の鬼斬の刃……アマテラスが握られていた。 「くくく……我らの血を吸って真っ赤に染まったツクヨミか……赤き太陽が全てを焼き尽くすように、我らを滅ぼした……忌々しい鬼斬の刃、アマテラスか」 「黙れ!」 紅雪の表情は怒りに満ちていたという。 こんな紅雪の顔は初めてだと、後に天皇は手記に内密に残していた。 それほどまでに、紅雪は酷い怒りにとらわれていたのだろう。 「何故曇暗様に取り憑いた!! 曇暗様は鬼などではなかったのに!!」 「くくく、何を言っておる。この男は立派な鬼の子だ。才ある鬼の血と、純粋な鬼の血が混じった、優秀な鬼だ!」 「黙れ!!」 紅雪は曇暗に取り憑いた海松橿姫の顔の真横に鬼斬の刃を突き刺した。 「血など関係あるものか!! 曇暗様は誰よりも人らしいお心を持っていらした!! 誰よりも帝を慕い、誰よりも率先して帝の盾となった!! 返せ!! 曇暗様を返せ!!」 「馬鹿を言うな。こんな恰好の依代をそう簡単に手放すものか!」 紅雪は自分の体に衝撃が走るのに気がついた。 そのときには既に紅雪の体は曇暗から引き剥がされ、天皇の部屋にあった大きな柱に打ち付けられていた。 「ぐっ……ぅ……げはっ!!」 海松橿姫の背中には、いつもとは様子の違う異様な空気を纏った十二天将軍、貴人が立っていた。 「貴様……曇暗様の力を……ぐっ!」 「使えるものを使って何が悪い? この男の体はいい、力がみなぎるわ!」 「はっ……はぁはぁ……」 紅雪は一瞬だけ絶望を覚えた。 流石に曇暗の十二天将軍相手では、勝てるものではない。 体術全般ならば、曇暗よりも達者な自信はあった。けれど、十二天将の力は、紅雪が知る限り自分ではどうしようもない力だった。 あれは、式神という名を借りた神だ。 紅雪に神を斬るほどの力は、備わってはいなかった。 「……曇暗様」 紅雪は悔しさがこみ上げて、体が震えた。 敵前で涙を流すことはできなかったが、それでも悔しかった。 自分には、帝を守ることも、曇暗を救うこともできない。 そう思うと、自分が許せなかった。 「曇暗様……!! 曇暗様……!!」 ぐっとアマテラスを握り、彼女は震えたままだった。 「私はお前の祖先の速来津姫のように残酷ではない。せめて愛する男の手で死ぬがよい」 海松橿姫は、紅雪の襟首を引き寄せ、紅雪が捨てた刀を抜いた。 「哀れなことだ。あの女の子孫でなければ、こんな思いをせずこの男と添い遂げられたかもしれぬものを」 海松橿姫が紅雪の首に刀を突き立てたそのときだった。 彼女は目を見開いた。 どんなに手を動かそうとも、その刀は紅雪の首に突き刺さることはなかった。 「なっ!? 何故だ! 何故動かぬ!!」 「……曇暗……様?」 『紅雪……俺を早く斬れ!』 紅雪の目には、薄っすら自らの肉体の腕を押さえる曇暗の姿が映って見えた。 彼は必死に、自分の体の中の海松橿姫を抑えていたのだ。 「曇暗様!!」 『俺がこうしてこの女を止めていられるのはわずかな時間だ! 早くしろ!!』 「できませぬ!! あなたを斬ることなど、私にはできませぬ!!」 『紅雪!』 「いやでございます……!! 曇暗様!!」 曇暗は、まるで泣く子をあやすように言葉をかけた。 いつもの曇暗からすれば信じられないほどに優しい声だっただろう。 『紅雪……俺はお前を信じておる』 「え……?」 『お前には俺の中の鬼を斬る力があると』 それは、紅雪に自分を斬らせるための方便だったのだろう。 しかし、その言葉は紅雪に大きな力を与えた。 「曇暗様……」 『紅雪、お前は俺をきっと解き放ってくれる。この呪われた運命から。運命は、変えてなんぼなのじゃろう?』 「……はいっ」 そのとき、紅雪の涙が一滴、鬼斬の刃であるアマテラスに零れ落ちた。 アマテラスは青い光を放ち、その刀身を青に変えた。 「これは……」 「ぐっ! こざかしい!!」 とうとう、曇暗の力はつきたのか、海松橿姫は頭を左右に振りながらも自分の意識を取り戻した。 しかし、時は既に遅かった。 「曇暗様、今お助けいたします!」 紅雪は、海松橿姫の顔を掴んで立ち上がると、右手を蹴り飛ばして刀を落とした。 顔を抑えたのは、呪文を唱えられないようにするためだったのだろう。 「ぐっ!!」 「曇暗様の中の鬼は、私が斬り捨てる!!」 紅雪は迷うことなく曇暗の体に青い刀身の刀を突き刺した。 今思えば、紅雪と曇暗の強い思いが、アマテラスと化した鬼斬の刃を一時的にツクヨミに戻したのかもしれない。 「あああああああああああああ!!! おのれ……!! おのれ鬼斬の娘!! 許さぬ……絶対に許さぬ!! このままでは終わらぬぞ!! 鬼門が開いている限り、私は何度でも貴様と帝を狙う!!」 それを最後に曇暗は倒れた。 ただ、彼の体には傷一つついておらず、忌々しそうに黒い人魂がその周囲を飛び交っていた。 「……鬼門を……閉じなければ……でも、どうすれば……」 そのときだった。 曇暗の懐から二枚の符がふわりと宙を浮き、白と黒の光を放った。 【鬼斬の娘よ】 【我らの言葉に耳を傾けるがよい】 紅雪は驚きのあまり手に持った刀を強く握りなおした。 【案ずるな、我が名は六合】 【我が名は天空。曇暗より名を聞いておろう】 「六合と……天空……まさか十二天将軍の!?」 【左様。鬼斬の娘よ、時間がない。手短に話すぞ】 「はっ!」 紅雪は頭をたれて二人の神の言葉に耳を傾けた。 【一刻も早く鬼門を閉じねばならぬ。しかし、曇暗は憑依の後でろくに術を使えぬだろう】 【他の陰陽師たちも皆戦いで傷ついておる】 「では、どうすれば!」 【今動けるのは、そなただけだ】 【そなたが鬼門を閉じるのだ】 「私が!?」 紅雪はさぞ驚いただろう。 彼女は陰陽術など一度として使ったことがないのだから、無理もない。 「しかし、私には陰陽術の心得はございません!」 【案ずるでない。我ら十二天将軍が手助けしよう】 【ただし、お前が鬼門を閉じるとなると色々と制約が生じる】 「制約……」 【左様。鬼斬の血を絶やしてはならぬ。これより我らはそなたの魂を二つに割り、一つを錠、一つを鍵とする】 【お前の魂の片割れは錠となり我らと共に鬼門を封じ、鍵は血を解して現世を生きる。それが今できる鬼門を封じる最善の方法】 「魂を……二つに……」 聞けば聞くほど恐ろしい話だ。 紅雪の魂の半分は、いつ終わるとも分からない永遠に近い時間鬼門の封印をしなくてはならない。 そしてその半分は、何百年、何千年のときを巡り現世を生き続けなくてはならない。 どちらにしても、終わりなき永遠の苦しみだろう。 【どうする?】 【今はこの方法しかないが、やるか? やらぬか?】 紅雪は倒れる曇暗を見てぐっと唇を噛んだ。 「最後に、曇暗様とお話してもよろしいですか?」 【あまり猶予はないぞ】 「分かっております」 紅雪は倒れる曇暗を抱き起こした。 そして、優しく彼を起こした。 「曇暗様、曇暗様。目を開けてくださいませ」 「紅雪か……すまぬ、転寝をしておったか……?」 「くすくす……まだ春も来ていないのに、早とちりな曇暗様」 紅雪は泣きたいのを我慢して曇暗に微笑みかけた。 「曇暗様、紅雪からお願いがあるのです」 「どうした……お前が願いなど珍しいのう」 「ふふ、たまには我儘を言わせてください」 紅雪は曇暗の頭を膝に乗せて、その頬を優しく撫でた。 「曇暗様。私たちの可愛いややをお願いします」 「当たり前だろう……? どうしたのだ一体」 「それから、絶対にややに伝えてください。お前もよい子を産みなさいと。その先もその先もずっとずっと、命を紡ぎ続けなさいと」 「紅雪……?」 「曇暗様……きっとですよ? 絶対に私たちの絆を絶やさぬよう、決して子孫を絶やさぬよう、伝えてください」 紅雪はそっと曇暗の髪を撫で、彼を床に寝かせると立ち上がった。 「紅雪……!? ぐっ!!」 曇暗は体を起こすこともままならず、紅雪が内裏から出て行く姿を目で追うことしかできなかった。 「さようなら。曇暗様」 「紅雪!?」 「お慕いしております曇暗様……これから何百年、何千年経とうとも、私はずっとあなたをお慕いしております、愛しております」 「待て紅雪……何をするつもりだ!!」 振り向いた紅雪の顔は今までで一番美しいとそのとき曇暗は感じたという。それは偏に大切なものを守りたいという強い思いが彼女を輝かせていたためかもしれない。 紅雪は宮中を出ると、自分の背後に立った六合と天空に言った。 「鬼門までは行かなくてよいのですね?」 【肉体はここで捨てる。もう必要はない】 「分かりました……」 【では我らの言うとおりに】 「はい」 彼女は鬼斬の刃を天にかざした。 「我、源紅雪、十二天将軍、六合・天空の名の下にこの御霊を二つに裂き、錠と鍵とする!! 我、十二の神の力を借りて、冥府と現世の狭間の門を閉じん。鍵は血を介し、その血が絶えぬ限り未来永劫錠と交わることを禁ずる……!!」 彼女の後ろに立った六合と天空が光の柱となり、彼女の体からも光の玉がすーっと抜け出した。 それは二つに別れ、一つはどこへともなく飛んで行き、もう一つは六合・天空の光を纏い、黒い人魂を絡め取りながら鬼門のほうへ向かっていった。 【十二天将軍たちよ、共に眠りに付くときだ】 【さぁ、行こうぞ】 その瞬間、曇暗の懐にあった、六合天空を除く十枚の符が一斉に宙を舞い鬼門のほうへ飛び去ってしまった。 「どういうことなのだ……一体、何が起きている!!」 曇暗は体を引きずりながら鬼門のほうを見た。 鬼門はまぶしい光と共に少しずつ黒い人魂を飲み込み、閉じていった。 『曇暗様……愛しております……ずっとずっと』 鬼門が完全に閉じる寸前に、彼は紅雪の声を聞いた気がした。 全てが終わる頃には、夜が開け、京の都はすっかり静けさを取り戻していた。 その後、曇暗の元に、宮中の前で紅雪の亡骸が発見されたという知らせが届いた。 曇暗は酷く嘆き悲しんだそうだ。 けれど、紅雪の最後の言葉を守り、彼女のとの間に生まれた子を立派に育て上げた。 全てを見ていた天皇は、曇暗にことの始終を伝え、紅雪が鬼門を閉じるための錠となったことを教えた。 そして、その魂の片割れは、鍵として永遠に生き続けることも。 そして、曇暗と紅雪の子がある貴族と結婚し、子を産んだその日。 曇暗はその元気な赤子の姿を見ると、まるで全ての役目を終えたかのように、ぽっくりとこの世を去ったそうだ。 今の土御門の血筋は、曇暗の血筋ではなく、彼の兄たちの血筋だ。 曇暗と紅雪たちの子孫はその後、自分たちの血筋を絶対に絶やしてはいけないという言いつけを守り、その血を現代までしっかりと引き継いだ。 そして、一番新しい鬼斬となったのが椿というわけだ。 椿の魂には、紅雪の鍵としての魂も宿っていたのだろう。 しかし、何も知らなかった俺たちは、彼女を一度死なせている。 子を成す前に…… 全ては、あの日、椿が死んだ日に歯車が回り始めていたのだ。 |