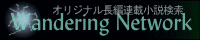第12話 安倍曇暗と源紅雪 其ノ二
|
茨木を退治した日から、ぱたりと紅雪は曇暗の元へ来なくなった。 鬼退治をしない日でも、たまには家を訪ねてきた紅雪がこうも来なくなるのは珍しかった。 「……ふん、一丁前に無視を決め込んだというわけか」 曇暗は妙に苛立っていた。紅雪が、自分に何も話さずに距離を置いたのだから無理もない。 それこそ、友としてのお前を信じたいなどと言われた後だったからかもしれない。 「曇暗様、少々苛立ちすぎですよ」 「小瑠璃か。で、どうだ向こうの様子は」 「鬼退治も茨木の一件で落ち着いちゃってますからね。あちらも退屈そうに庵で書物を読んだり、歌を詠んだり、鍛錬したり。普通の日々を送っていらっしゃいますよ」 「ようは生活の中から俺に会うという部分を取り除いて過ごしておるわけだな」 その小瑠璃の報告に、曇暗はますます苛立った。 自分に落ち度があるならまだしも、まったく意味の分からない状況で距離を置かれては無理もないかもしれない。 「ふん、そっちがその気ならば俺から出向いてやろうではないか」 「え!? 行くんですか!?」 「意味の分からない仕打ちを受けるのは何より嫌いなのだ。理由の一つも聞かせてもらわねばなるまい」 その夜、曇暗は夜闇に紛れて紅雪の庵を訪ねた。 それはとても家とは呼べぬ粗末なつくりの庵で、雨風がしのげればよいという程度のものだった。 その庭先からこっそりと気配を消して、曇暗は紅雪の庵に近づいた。 幸い紅雪は夜着に着替える最中なのか、曇暗の存在に気がついていなかった。 「おい」 「!?」 紅雪は慌てたように庭先のほうを振り返り、そして顔を青くした。 慌てて着物で胸元を隠したが、曇暗の前に晒してしまったそれは隠すことができなかった。 「やはりな」 「……着替えるから、少し待っていてくれないか」 「……ああ」 曇暗にしては妙に素直な行動だったと思う。 後ろを向けといわれても、いつもの曇暗なら一切動かなかったろう。 「もう結構です」 まるで別人のようだった。 振り向いたときの紅雪の姿は、いつもとはまったく違っていた。 「自分が女子だということを隠すために距離を置いたのか」 「あなた様のその反応を見る限り、私が女だということを知っていらしたのですね……」 紅雪は少しだけ顔を赤らめて深々と頭を下げた。 「今まで、騙していて大変申し訳ありませんでした。数々のご無礼をお許しください」 しおらしい紅雪を見て、曇暗はさぞ複雑な気持ちになっただろう。 頭の回転がさほど遅くない曇暗は、このときに何故紅雪が自分と距離を置いたのか瞬時に察してしまったのだ。 胸元に触れられれば嫌でも自分が女だとばれてしまう。 それは紅雪にとって、今の心地のよい曇暗との友人関係に亀裂が生じる可能性があったからだ。 それを考えると、紅雪は不安で仕方なかったのだろう。 「気がついておらんとでも思ったか? 元々男と女では体の作りが違う。それを見抜けんほど、俺はうつけではない」 曇暗は目を伏せた。 紅雪はそれに対して何も返事をしなかった。 「帝は……知っておるのだな?」 「はい」 「そうか……」 曇暗は紅雪をまっすぐに見ることができなかった。 「そもそも、鬼斬とは女しか生まれぬと聞く。だから、俺は最初から知っておった」 「私は、あなた様とずっと一緒にいたいと思っておりました。けれど、女と分かってしまえばそうもいかない……私はそれが怖かった。自分可愛さにずっと嘘をついておりました。申し訳ありません」 「もうよい」 何度も何度も頭を下げる紅雪の姿を、曇暗は見ていられなかった。 自分と一緒にいたいがために、自らの性別すらも偽っていた紅雪を責める気にはなれなかったのだろう。 曇暗は、紅雪の家に上がると、くいっと彼女の顔を引き寄せた。 「たっ……曇暗様!?」 「俺はお前が嘘をついていることを知っていて知らんふりをしていたのだ。お前をとがめるつもりはない」 「なっ、何をなさるのですか! お戯れはよしてください!!」 紅雪は無理矢理曇暗の体を引き離した。 「戯れ……か」 「曇暗様?」 曇暗はすぐに紅雪から目を逸らして立ち上がった。 「いや、なんでもない」 「とにかく、私と会うのはこれきりにしてください。鬼を退治するときだけは……男としてお付き合いいたします。けれど……女とわかってはもう共にいることは……」 「……馬鹿なやつだ」 「え?」 曇暗はそういい残すと、紅雪の庵から立ち去った。 紅雪はこのとき、もう曇暗と会うことは帝の命を受けたときだけだと思っていた。 しかし、曇暗はそんな馬鹿正直な男ではなかったのだ。 次の日、剣の稽古をしていた紅雪のところに突然使者が現れたと思うと、上等な着物を何着も置いていった。 その着物は全て女の着るものだった。 「一体どういうこと……?」 もちろん送り主は曇暗だった。 曇暗のその行動に、紅雪は戸惑っていた。 「宵の月 雲に陰りて 我隠す……」 紅雪はその夜、ぼんやりと月のない空を見上げて歌を詠んでいた。 その手には、曇暗から贈られた着物がしっかりと握られていた。 「何だ、まだ着ておらんかったのか」 「!?」 紅雪は目を見開いた。 夜の闇から現れたのは、呆れたような顔をした曇暗だった。 「たっ、曇暗様!? 何故来たのですか!!」 「何故と言われてものう。送った着物を着たお前を見に来ただけじゃ」 「わ……私にこのような上等な着物は似合いませぬ」 「着てみねば分かるまい。何だ、まさか着かたがわからんのか? 手伝ってやろうか?」 「け、けけけ結構です!!」 顔を真っ赤にする紅雪だったが、どうやら本当に女物の着物を着たことがないらしい。 何しろ宮中の姫君たちが着るような十二単を一人で着られると思っているあたりが、まず無理な話だ。 「くくく。まったく、男でも女でも意地っ張りなところは変わらんな。小鷺、手伝ってやれ」 「はい、曇暗様」 しばらくして、すっかり着物を着替えて化粧をした紅雪を見て、曇暗は目を見開いた。 想像以上にその姿は美しかったからだろう。 透き通るような白い肌、絹を紡いだような白い髪、そして宝玉のように輝く赤と青の瞳は、そこらの姫君になど負けない美しさだった。 「これは驚いたな」 「あ、あまり見ないでください。お恥ずかしゅうございます」 「俺が見たくて贈った着物を見て何が悪い?」 軒先にちょこんと座った紅雪の隣に曇暗は腰掛けた。 「御簾で顔を隠してろくに表情も伺えぬ姫君なんぞより、こうして美しい顔を見せてくれる女子のほうがやはりよいのう」 「そんな……宮中の姫君たちは皆さぞお美しいのでしょう? 私など、女房にも劣りますわ」 「ふん。女のお前は随分としおらしいのう。だが、そういうのは嫌いではない」 上機嫌に曇暗は言った。 「小瑠璃、酒をもってこい」 「はいはい、そういうと思ってもう用意してありますよ」 曇暗の式神は杯を曇暗に渡し、酒のほうを紅雪に渡した。 「紅雪、酌をせい」 「え?」 「酌じゃ酌。美しいおなごに酌をしてもらって夜桜を眺めるなど、最高の贅沢だとは思わんか?」 「曇暗様……」 紅雪は慣れない手つきで曇暗の杯に酒を注いだ。 曇暗はその日、今までに見たことがないほどに上機嫌で酒を飲んだ。 隣に寄り添う紅雪もまた、今までにないほどに幸せそうだったのは言うまでもない。 「紅雪」 「はい?」 紅雪の名を呼んだ曇暗の顔は、酒に酔ったせいなのか少し赤かった。 紅雪はこんな曇暗の顔は見たことがなかっただろう。 「俺が何故、お前が女子と知っていてあえてお前の嘘に付き合ったか、分かるか?」 「……いいえ。仕事がしやすいから、ではないのですか?」 その紅雪の言葉に、曇暗は失笑したようだった。 「まぁ、俺の今までの態度ではそう思われても仕方ないのう。しかしな、紅雪よ。別に俺は鬼斬の力が欲しくてそんな面倒なことをしておったわけではないのだぞ?」 「では一体なぜ?」 杯を軒先に置いた曇暗は、紅雪のほうをじっと見据えた。 その熱っぽい視線から、紅雪は逃れられなかった。 「俺が欲しかったのは、鬼斬の力ではない。お前だ」 「!」 その瞬間だった。 曇暗が紅雪に初めて口付けをしたのは。 「たっ、曇暗様!!」 「紅雪、逃げんでくれ」 「!」 まるで、すがる様に抱きしめられて、紅雪は動くことができなくなってしまった。 「曇暗様……」 「俺は、お前でなければ心を許せぬ」 「いけません、曇暗様。あなたにはもっとふさわしい姫君がおります」 「他の姫など知らぬ。俺は今まで苦楽を共にしてきたお前でなければ駄目なのだ。お前と俺は似ている。異形の血が流れていても、世間の目がありながらも帝のために戦うお前だかたこそ俺は惹かれた」 「曇暗様……」 曇暗の手にはどんどん力がこもっていく。 「紅雪、お前の本心はどうなのだ?」 「え……」 「お前の言葉は俺の世間体を考えたものばかりだ。俺が聞きたいのはお前の本当の心のうちだ」 紅雪はその言葉に、しばらく黙ったままだった。 言うのをためらい、言葉にできないような顔だった。 曇暗はせかすことなく、紅雪の言葉を待った。 「私だって……曇暗様の傍にいたいです。ずっとずっと、その時間が続いて欲しいからこそ、私は自分を男と偽っておりました」 「紅雪……」 「お慕いしております、愛しております。本当は独り占めしたくて仕方がないです。曇暗様! 曇暗様……!」 このとき、二人の心は初めて結びついた。 ずっと惹かれあっていても、立場と身分を考えたら本心を伝えられなかった二人の心はやっとここに着て通じ合えたのだ。 それからの二人は、毎晩のように月を見ながら語り合い、毎晩のように愛を語り合った。 もう、誰も彼らの邪魔をできるものはいなかった。 二人を引き合わせた天皇が二人の仲を祝福した時点で、口を出せる者などいなかったのだ。 天皇は日ごろの二人の働きを褒め、立派な屋敷を褒美に与えた。そこで二人は晴れて夫婦となったのだった。 そうして月日が流れ、とうとう紅雪は曇暗の子を身ごもった。 幸せな時間がずっと続くと、誰も疑いはしなかった。 曇暗も、紅雪も、そして二人を引き合わせた天皇さえ…… しかし、紅雪が曇暗の子を産み落としたすぐ後、今日の都は壊滅の危機に陥ることになる。 歴史から葬られた大事件が、彼らの幸せな時間を闇に沈めたのだった。 |