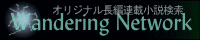第11話 安倍曇暗と源紅雪 其ノ一
|
次に話すのは平安時代のことだ。 この時代は我々御三家の祖先、安部晴明や蘆屋道満、賀茂保憲など名のある陰陽師たちも活躍した陰陽師の全盛期とも言える時代だ。 そんな時代に、天皇の命どころか京の都の危機を救ったというのに、今では全く名が残されていない、陰陽師と武将がいた。 陰陽師の名は安部曇暗(あべのたんあん)、現代にその名が記された文献は存在しない。 陰陽師協会が内密に保存していた、ほこりを被った何百年も誰も目を通していなかったような、廃れた文献を除いては。 曇暗の父親は、かの有名な安部晴明だったのだ。しかし、記録には晴明の子は安倍吉昌と安倍吉平の二人しか登場しない。 しかしその二人とは比べ物にならないほどに、曇暗の陰陽術は見事なものだった。 それこそ、父親を超えるのではないかと言われるほどに…… それほどの実力を持ちながら、曇暗が何故歴史の表舞台に出てこなかったか、それは簡単な話だった。 曇暗は晴明の隠し子だったのだ。それも、人との間にできた子ではないとも記録されている。 晴明と鬼の間に生まれた子、異形として曇暗は恐れられ、その存在を隠されることになった。 本当に鬼の子なのかは定かではないが、その当時鬼は異形の象徴のようなものだった。 だからこそ、その血が混ざっているとされた曇暗は誰よりも恐れられたのだろう。 しかし皮肉な話だ。 別に曇暗が鬼の子であったとしても、決して異形ではないからだ。 前にも述べたように、鬼は土蜘蛛が天皇側の人間と関わりを絶ち、独自の文化を築いた存在に過ぎない。要するに鬼もまた元を辿れば人ということだ。 まぁこの時代にもなると、虐げられたことにたいする恨みつらみが爆発し、人ならざる異形と化した姿の土蜘蛛たちが大半だった。 もう人とは到底呼べぬ恐ろしいものを総称して、人々は鬼と呼んだのだろう。 晴明は、もしかしたらただ単に土蜘蛛の生き残りの、異形と化していなかった美しい娘と契りを結んでしまっただけなのかもしれない。 しかし、人とは自分と違うものを極端に嫌う存在。 だからこそ、その自分たちとは違うものとの間に生まれた曇暗は"異形の子"として気味悪がられたのだろう。 「曇暗様、曇暗様。お客様でございますよ」 「うん? いかんのう、居眠りをしていたわい」 「くすくす。桜の季節、春眠暁を覚えずと言います。仕方ありますまい」 「ああ、妙な夢を見ておった」 「まったく、真昼間から寝こけているとはいい身分だな曇暗」 曇暗がふと軒先から座敷のほうに振り返ると、呆れた表情で一人の武士の若者が立っていた。 「なんだ紅雪(こうせつ)か」 曇暗は入ってきた若者の姿を見て、大きくため息をついた。 その武士の若者の姿は白髪に、右が赤い目、左が青い目と、明らかに普通の人間とは言いがたい姿だった。 しかし曇暗は慣れた様子で、驚くこともせずに紅雪を一瞥した。 「何だではない。まったく、陰陽師の名家の人間が仕事もしないで何をしておる」 「ふん。仕事なんぞ俺のところにはたいした仕事は回ってこん。それよりも源家の紅雪様がわざわざお出ましとは、何事じゃ」 「一条戻橋で悪さを働く鬼を退治する。手を貸してはくれんか?」 「一条戻橋? ああ、茨木か」 曇暗は、紅雪の話に興醒めしたようにため言った。 「知っているのか?」 「知っているも何も、あの鬼は今吉昌と吉平が追い回しておるだろう」 「ああ、兄上二人も随分手こずっておいでだ」 「ふん……」 そのときの曇暗の様子は、すっかり話半分だったという。 頬杖を付き、紅雪のほうも見ずに庭先をぼんやりと眺めていた。 「帝より、俺とお前で迅速に茨木を封じよとの勅命だ」 「まぁ茨木が暴れ始めてから随分時間が経っておる。そろそろとは思っておったが……なるほど。兄二人の尻拭いをせいということか」 再び大きなため息を付いて、曇暗は紅雪を見た。 「お前が直接俺のところに赴いたということは、仕事は今晩早速ということだな?」 「ああ」 「やれやれ、急じゃのう。しかし帝直々の命令とあれば、動かぬわけにはいかぬか」 安部曇暗と源紅雪は、ある鬼を退治したときからの仲だった。 酒呑童子という、恐ろしい鬼をこの二人の圧倒的な力で封じて以来、彼らはこうして天皇からの命令があったときには共に動くようになった。 「さぁて。ならば準備をしてさっそく行くとするかのう」 「まだ昼間だぞ?」 「すぐに鬼退治などするものか。散歩がてら椿餅でも食べながら夜を待つのだ。お前も付き合え」 最初、紅雪はこのつかみどころのない曇暗の扱いに困ったという。 何を考えているのかも分からず、何かを恐れることもしないこの男が不気味に感じたのだろう。 しかし、曇暗という男を知るうちに、逆に好感を持ったのだそうだ。 詳しくは記述されていないが、同じ"異形"であるが故の親近感ではなく、紅雪は曇暗の中にある己と同じ志に惹かれたとある。 「のう紅雪、お前は椿餅は好きか?」 「好きも嫌いも……食ったことがない」 「何? 食ったことがないと? お前、そんなに内裏に出入りしておらんかったかのう」 その当時椿餅は一部の貴族しか口にできないものだった。蹴鞠に呼ばれた貴族たちが、そのあとに食すくらいであり、宮中に呼ばれることのない者ではまず食べる機会はなかっただろう。 「俺は身分の卑しい武士だ。専ら鬼退治ばかりで、宮中に参内することなどまずない」 「それは知らんかったわい」 「どれだけの付き合いだ。少しは俺の状況くらいは知っておけ」 「興味などないさ。お前の身分やら立場……見た目さえ、どうあれお前はお前なのだから」 曇暗は空を見上げて、手に持った椿餅をほおばった。 そして、もう一つの椿餅を懐から取り出すと、紅雪に差し出した。 「食え」 「このような高級品もらえぬ……」 「なに、美味いものも一人で食ったところで味気ない。分かち合ってこそ真に美味いというものだ」 曇暗は、紅雪と一緒にいるときだけはよく笑ったという。 普段は全くといっていいほど表情を変えない曇暗が、こんなにも感情を表に出すのは珍しいことだった。 紅雪は曇暗にもらった椿餅を一口ほおばると、輝かんばかりの笑顔を浮かべた。 「これは美味い。こんなものは初めて食べた」 「それはよかった」 紅雪がすっかり椿餅を食べ終わった後、曇暗はふと口を開いた。 「のう紅雪。俺とお前は知り合って随分経つが、お前は俺のことをどこまで知っておる?」 「どこまで……? 才ある陰陽師ということしか俺は知らん。陰陽術に長けておるのは、かの安部晴明殿の息子だからかもしれんが、それ以上に何があるのだ?」 「嘘をつかんでもよい」 「いや、俺は本当にそれしか知らぬ」 「……それが本当なら、お前はよほど世間の噂に疎いと見える」 呆れたように曇暗はため息をついた。 「すまん。世間の噂にはあまり耳を貸したくないのだ。心がざわついて、刃が鈍る」 そこで曇暗はすぐに察した。 世間の噂というのはくだらないものが多い。 それこそ、自分や目の前にいる紅雪は、好奇の目で見られていることが大半だ。 噂など耳にすれば、自らが不快な思いをするだけになる。 「まぁよい。俺はのう、鬼の子じゃ」 「は?」 「父親は確かに阿部晴明に間違いない。しかし、母親は二人の兄とは違うのだ。俺も会ったことはないが、話によれば鬼だといわれておる」 「鬼……」 「そうじゃ。だから俺は二人の兄のように宮中にも参内しない。まぁ、帝のほうから出向いてもらえるというのも随分な立場じゃがのう」 曇暗は知っていた。 天皇が自分と紅雪を引き合わせたことを。 多分、天皇はどこかで曇暗を一人にしておけなかったのかもしれない。 しかし、彼が紅雪と親しくなっていくにつれて、曇暗の心には大きな不安が生まれていた。 「のう紅雪。お前は俺が鬼の子だと知って、生かしておくか?」 「なに……?」 「俺はお前をがどんな存在なのか、よう知っておる。白き髪に赤と青の瞳を持つ者は鬼斬と呼ばれ、鬼どもに対して絶対的な力を持っておるのだろう?」 「本当に……よく知っているのだな」 「これでも陰陽師の端くれじゃからのう」 曇暗は紅雪に背を向けたまま言った。 「紅雪。俺は自分がよう分からんのだ。半分鬼の血が混じっているのだとすれば、俺はいつか帝に仇なす存在になるやもしれん……あのお方はお優しい。俺の手で傷つけるなど、絶対にしとうない」 「………」 「鬼斬のお前が、俺を鬼と判断したのならば、今ここで切り捨ててはくれんか?」 「なっ!? 何を言っているのだお前は!!」 流石にそんなことを言われては紅雪とて焦るだろう。 目の前にいるのは自分よりははるかに人の姿をした男だ。 斬れといわれても困るのは当然だ。 「お前の目には俺の中にいる鬼が見えるか?」 紅雪は、しばらくの間曇暗をじっと見据えていた。 その手は、腰に差した刀の柄にしっかりかかっていた。 曇暗に言われたとおり、まるで彼の中の鬼と向かい合っているかのように紅雪はピクリとも動かなかったという。 しかし。 「いや。今はお前を斬るのはやめておこう」 「なに?」 不意に紅雪は刀から手を放し、ひらひらと舞い散ってきた桜を一片手に乗せて言った。 「今お前を斬れば、お前と引き合わせてくれた帝のご意思を無駄にすることになりそうだしな」 「その判断が、後に帝の命を危機に晒すとしてもか?」 「ふん、お前がもし帝に仇なしたときは、誰よりも先に俺が首をはねてやる。同じ異形のよしみでな」 「紅雪……」 紅雪は、ふと曇暗の肩を叩いて笑った。 「何より、お前は俺の大切な……なんと言えばいいのだろうな。そう、友だ。最後まで友である安部曇暗を俺は信じたい」 「似合わんことを言うでない。普段言わんことを口走ると死相が出るぞ」 「おお怖い。そりゃあたまらんな桑原桑原」 しかし、このときの曇暗の思いは複雑だったという。 曇暗は、紅雪に対してある特別な感情を抱いていたからだ。 「ええい!! 忌々しい人間共!! 切り裂いてくれる!!」 「さぁて、切り裂かれるのはどっちだろうな茨木童子」 「俺たち二人を相手にさせてしまったのは、失敗だのう」 二人は当時の天皇から、鬼退治の分野では絶対的な信頼を得ていた。 曇暗と紅雪が組んだときの鬼退治の成功率はほぼ100%と言ってもよかったそうだ。 陰陽術で右に出るものがいない阿部曇暗、そして鬼に対して絶対的な力を誇る源紅雪が相手では当時の鬼たちでさえ裸足で逃げ出しただろう。 「臨める兵、闘う者、皆、陣をはり列を作って、前に在り!」」 曇暗は、晴明と同じく十二天将を自在に扱えたという。あんな強大な式神を12体いとも簡単に扱えたというのだから、その力は計り知れない。 「勾陣!! 大陰!! 奴の動きを封じよ!!」 曇暗が茨木を倒した際に呼び出した十二天将は、黄色い竜の姿をした勾陣と、少女の姿をした大陰だったという。 大陰はふわりと茨木の視界をさえぎり翻弄し、その間に勾陣が茨木を締め上げた。 「ぐあっ!! 離せこの!!」 「鬼斬の刃よ、我源紅雪の名の下に悪鬼を切り捨てる力となれ!!」 「なっ!?」 そうして身動きが取れなくなった茨木は紅雪の鬼斬の刃に貫かれ一気にうちに溜め込んだ力を外に放出され、小さな小鬼と化す。 「今だ曇暗!!」 「ああ!」 曇暗は素早く印を切り、茨木に向かって符を投げた。 「天を我が父と為し、地を我が母と為す……六合中に南斗・北斗・三台・玉女在り、左には青龍、右には白虎、前には朱雀、後には玄武、前後扶翼す!! 急急如律令!!」 茨木の体は光と化し、符の中に吸い込まれていった。 そして符にはしっかりと茨木童子という文字が刻まれた。 この茨木の封印を守る役目が、後に土御門家になったのは土御門家の大本である安部家の人間が茨木を封じたためだった。 そう考えれば茨木の盗難により、安部家の末裔である俺と鬼斬の娘である椿が出会ったの、なんとも運命のいたずらなのか必然なのか。 不思議なものを感じずにはいられない。 「終わったのう」 「ああ、相変わらずのお手並みだな」 二人は月に照らされ向かい合うとただ微笑みあったという。 「ん? 紅雪、怪我をしたのか?」 「え?」 ふと、曇暗は紅雪の胸元の傷に触れようとした。 「や、やめろ!!」 紅雪は思わずそれを振り払ったという。 もちろん、曇暗は怪訝な顔をした。 「何だ、手当てをしようとしただけだろう?」 「いらぬ……!!」 「紅雪……」 その瞬間、紅雪は我に返ったのだろう。 左右に首を振って曇暗に言った。 「すまん、今日は少し調子が悪いようだ。この傷はかすり傷にすぎん。気にしないでくれ」 「……お前がそういうならそうしよう」 「物分りがよくて助かる」 紅雪は刀をしまい曇暗に背を向けた。 「今日は先に帰らせてもらう。またな」 「ああ」 紅雪は咲く桜舞い散る夜の闇に紛れて、曇暗の前から去っていった。 曇暗はただ、その背中をやるせない気持ちで見送っていた。 |