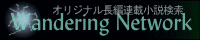第14話 波打際の二人
|
私と星弥は海辺の砂浜に座って、ぼんやりと波打ち際を眺めていた。 ザザーン、ザザーンって波の音が静かに響き渡ってる。 星弥と私はうちのお父さんとお母さんのお墓参りを済ませて、帰りにこうして海を眺めてる、って流れだ。 雅音さんたちは清姫の事件が解決したことをアッシーたちに伝えにいってる。 多分、アッシーは今回の事件解決に携われなかったことをかなりの勢いでぶーたれてるから、なかなか帰してはもらえないんだろうな。 「椿、ホントごめんな」 「もう。いい加減謝るのはなしって言ってるでしょ」 「でも……やっぱおじさんとおばさんが死んだのって、俺の心の歪みが原因だろ?」 「………」 私は、その言葉に俯いた。 なかなか、星弥の言葉に対する返答が見つからない。 でも考えあぐねいても出てくる答えは一個だけだった。 「星弥は……悪くないよ」 「椿……」 「そんな思いを抱くくらい、私を大事に思ってくれてたってことでしょ?」 星弥は驚いたように目を見開いた。 「正直、あんたに好きって告白されたときには心穏やかじゃなかったわよ」 「なんで?」 「あんたは私の幼馴染で弟みたいなもんだもん。あんたが私に向けていた視線て、どっか恋愛とは違うもんだと思って安心してたってのもあるけど」 「気がついてたのか」 「そりゃあ、どんだけ付き合い長いと思ってんのよ」 私は膝を抱えなおして、遠くを見た。 「あんたはいつでも私に頼ってきてたでしょ?」 「ああ」 「でもいつからかなぁ? 小学校の夏くらい? あんた突然変わったよね」 「え?」 「私に頼らなくなった」 私は幼馴染の小さな変化に気がついていた。 いつも椿ちゃん椿ちゃんって私の背中を追いかけてきていた星弥が、突然それをしなくなったんだもん無理もない。 それどころか、助けなくてもいいような場面で私を守ろうとして逆に怪我したり泣かされたり。 そりゃ気がつかないほうがおかしいわよ。 「椿にはかなわねぇよ……」 「ふふ、あんたはさ。格好付けたがるから駄目なのよ」 「は!? 俺かっこつけてなんかねーし!!」 「じゃあ何で言わないのよ」 「え?」 「私の目と髪のこと」 星弥は一瞬表情を青くした。 私はコンタクトをはずして、バレッタで止めた髪を下ろした。 そして、カバンに入っていたペットボトルの水を思い切り頭からかぶった。 「お、おい椿!?」 「知ってたんでしょ?」 「……傷つけたくなかったんだ。お前俺に内緒にしてたみたいだし」 「それが格好つけてるっていうのよ」 私はふぅっとため息をついてしまった。 まったく、言葉足らずの空回りってこういうこというんだろうな。 「最初から、あのときはごめんって言ってれば、こんな大事にならなかったんじゃない?」 「それは……」 「謝るのが格好悪いと思ってたんじゃない? そんで守りたいとか格好いいこといっちゃった結果がこれなんじゃないの?」 「ごめん……」 別に星弥を責めてるつもりじゃない。 でも、星弥は自分の幸せを見つけた。 だから同じ間違いは二度と繰り返してほしくない。 「これからは、一人で抱えないことよ」 「椿……」 「どうも私の周囲には一人で抱え込む人が多いから困るわ。ちゃんと話せば解決するのに」 「お前だって、人のこと言えねぇじゃん」 「ん、確かに」 私は苦笑いを浮かべた。 そう、一昔前。雅音さんに会うまでの私は、全部一人で何とかしようと思ってた。だけど、それってすごく苦しくて寂しいことなんだって今は気がついた。 アッシーにしたって、お兄さんのこと一人で抱えて苦しんでたけど、それをやめた途端に何かが大きく変わった。 自分自身で解決しようって意思は決して私は悪いことだとは思ってない。でも、一人で解決できないことだって世の中にある。 「あんたはさ、一人じゃないんだから」 「そう……だな」 「深散を泣かせたら、今度こそあんたを叩き斬るからね」 「おいおい……そりゃ物騒にもほどがあるぜ。そういや……」 「ん?」 星弥は思い出したように首をかしげた。 「お前はずっと俺がおじさんやおばさんを殺したかもしれないって気持ちを抱いてたんだろ? なのに、何であんとき急に俺に斬りかかって来たんだよ。あんときだけ様子が違ったって影井さんは言ってたけど」 「ああ……」 私は星弥に言われてあのときのことを思い出した。 あの時、ずっと頭の中で私の声が響いていた。 星弥は全てを忘れて幸せになろうとしてる、そう、私のお父さんとお母さんが死んだことすら忘れて。 許していいのか? 許してはいけない、許すな、許すなって。 その声は、少しずつ私の思いを浸食していった。 そして私はずっと抑えていた小さな憎しみを爆発させてしまったのだ。 「そっか……」 私のその曖昧であろう説明に星弥は波打ち際をじっと見つめた。 「あの声は、今思えばツクヨミの声だったみたいだけど」 「何でツクヨミはそんなことしたんだろうな」 「ん。何となく分かるよ」 「え?」 私は空を見上げて、目を細めた。 沈みかけた夕日がほんのちょっぴりまぶしい。 「ツクヨミは浄化の剣。私が今までツクヨミを使うことができなかったのは、多分星弥に抱いていた小さな憎しみのせい。浄化する者……相手の憎しみを斬る者が憎しみを抱いていたんじゃ、どうしようもないからね。ツクヨミは私に自分を扱うにふさわしい相手かどうか試したんだと思う」 「なるほど……しっかし驚きだよなぁ。今まで普通に生きてた俺たちが、鬼や物の怪なんてものに接触して生きていくことになるなんて」 星弥は盛大にため息をついた。 まぁ、無理もないと思う。 星弥は星弥で、実は結構鬼や物の怪に取り憑かれやすい体質してるみたいだし。 ま、私も人のことは言えないんだけどね。 何せ道成寺で星弥が清姫に取り憑かれたのと同時に、無意識に私は安珍に取り憑かれてたんだから。 後で雅音さんに聞いたら、確かに無害そうな坊主が憑いてたけど、忙しかったし無害そうだったから別に祓う必要もないだろうって祓わなかったらしい。 いやいや、忙しいからって取り憑いてるものを放置しないで欲しいとは思ったけど、それが功を奏して今回は事件が解決したわけだから何も言えないけどね。 安珍がすぐに表に出なかった理由は不明だけど、安珍は物の怪ではないほうの清姫の意思が戻るのを待ってたんじゃないかって見解だ。ま、真実は安珍しか知らないことだけど。 正直道成寺の物語が私たちの目の前で解決したっていうのは、ある意味すごいことだ。 「でも、清姫はちょっとだけ深散先輩に似てたな」 「え? どこが?」 「ん? 相手を思う一心で周囲が見えなくなるところとか」 「あはは、いえてる。そういう安珍はあんたによく似てたけどね」 「えーそうか?」 「そりゃ、清姫が勘違いするくらいですからね」 「何で俺をあの坊さんと勘違いしたのかなぁ。顔、全然似てなかったぜ?」 「そうねー安珍さんのほうがイケメンだった」 「いってくれるね椿ちゃん」 星弥の渋い表情に私はケタケタと笑った。 「ま、雰囲気って言うか心の中?」 「心の……中?」 「あんた自身も感じた部分、あるんじゃないの?」 星弥はそれにちょっとだけ目を見開いたけど、すっとそれを細めて苦笑いを浮かべた。 「んまぁ、そうだな」 そう、私たちの中には清姫と安珍みたいな子がいたから今回は解決したんだと思う。 深散の星弥への強い思いが青龍を呼び覚まし、邪悪な清姫を弱らせたことで、ほんの少しの間だけだったけど優しかった清姫の意思を目覚めさせることができた。 そして星弥の強い勇気が私のツクヨミを目覚めさせ、完全に邪悪な清姫を消し去れた。 きっと誰が欠けても解決できなかっただろう。 「でも、星弥。あんたこれからどうするの?」 「ん?」 「あっち、帰るんでしょ? 記憶も戻ったし。深散とは遠距離恋愛するつもり?」 「あー」 星弥は私のその問いに何か余裕の笑みを見せた。 愛しい恋人と離れ離れになるのに、なんなのよその笑顔は…… 「俺さ、こっちに転校することにした」 「は……はぁ!?」 「鬼や物の怪に取り憑かれやすい体質なら、自力で何とかする勉強しなきゃならないかなぁと思って」 「何その軽いノリ!? おじさんとおばさんなんて言ってるのよ!!」 「陰陽師協会からのお達しで、学費全額免除だろ? 寮費全額免除だろ? 生活費全額免除だろー……? なんか特典いっぱいついてるって報告したら両手放しで喜んでたよ。ほらうち、めっちゃ年の離れた弟いるじゃん? あいつの才能にぜひ金かけたいって悩んでたから、俺の残りの高校教育の金が一切かからないって聞いたらもう……」 「なんか、あんたの待遇が私と同じになってることに驚いたわよ」 確かに、星弥のうちには今小学校低学年の弟のはーくんがいる。はーくん……えっと藤原遥人くんは実は小さいながら能をやってるんだけど、ものすごい上手で才能がある。おじさんやおばさんは彼の才能をつぶしたくないと思ってるんだろう。星弥もその思いは一緒で、あいつのためなら大学行かないとか言い出してた始末だもん。 ある意味藤原家にはいいことなのかもしれないけど…… 「でも、なんで星弥が協会の保護を受けることになったのかしら……いまいち謎ね」 「なんか影井さんが電話して全部手続きしてくれたぞ?」 「……あはは、また雅音さんの謎の権力ね……もうそれなら納得できる気がするわ」 雅音さんと一緒にいるようになってから、どうにも京都でのあの人は怖いものがないように感じた。 睨めば大抵の人が怯む、そんな感じ。 ……ま、蘆屋家だけは特殊くさいけど。 深散のお兄さん、和葉さんも、なんだか雅音さんのことを思い出した瞬間に態度が大きく変わったし。 ううん、私の婚約者って何者なのかしら…… そう言えば深散は今まで借りていたマンションを引き払ったみたい。 なんでも和葉さんとの兄弟仲がよくなったから実家で生活することになったんだとか。 最近の深散はいつにもまして幸せそうだ。 そりゃそうよね。お父さんはまだ単身赴任中みたいだけど、家族のところに帰れたし、何よりもずっと好きだった星弥と相思相愛になったんだもん。今のあの子は無敵な気がするわ。 「お前たち、いつまでそうしておるつもりだ」 「へ!?」 「え!?」 私と星弥が同時に振り返ると、そこには二台の車が止まっていた。 一台は雅音さんの車、もう一台は多分深散の家のやつだ。 何でって、その車の前に深散と和葉さんが立ってるから。 てか深散んちの車すっご…… 黒塗りの高級車よねあれ、よく危ない人とか組織の黒幕とかが乗ってるあれよあれ…… 「日も暮れてきた。そろそろ帰るぞ」 「あ、うん」 私と星弥はお尻についた砂を払うと3人のところへ走った。 「星弥、お前は賀茂の家の車に乗って帰れ」 「え? あ、はい」 「星弥くん、今日はうちの家族と食事いたしませんこと?」 「うぇ!? い、いいんすか?」 「ええ、私の初彼氏をお母様に紹介しなきゃいけませんもの」 その言葉に星弥は珍しく顔をゆでだこみたいに真っ赤にしてる。 ふふ、本当に好きなのね。 「しかし深散、彼のどこがいいの?」 「え?」 和葉さんは訝しげに星弥を覗き込む。 その綺麗な顔が、星弥を見るときだけ妙に怖い気がするんですけど…… 「これといっていいところがあるようにも見えないんだけど……僕とこの彼どっちが好き?」 「もう、お兄様ったら」 深散は心底困った表情をして星弥の腕にしがみついた。 「そんな意地悪をいうお兄様は嫌いですわ」 和葉さん、がーんって言葉がよく似合う顔してる。 なんていうか、深散とのわだかまりなくなってから、和葉さん砕けた? っていうか深散のこと嫌ってるとばかり思ってたけど、正直シスコンよね……? ああ、好きと嫌いは表裏一体だっけ? 大好きな妹が、間違った方向に進んでいくのが許せなかったとかそういうのかしらね。 まぁ自分でそれに気がつかせるってあたり、和葉さんも相当我慢してたのかな。 本当はお前のここが駄目なんだ! って無理矢理にでも気がつかせて妹ぎゅーぎゅー抱きしめたかったに違いない。 でもタイミングって上手くいかないものね。 やっと妹が自分の間違いに気がついたころには、彼氏ができてるときたもんだもの。 ちょっと、可愛そうな気はするな。 「まったく、和葉のやつももう少しまともかと思うたが……」 「ふふ、いいんじゃない? 深散も嬉しそうだし」 「まぁ、それが最良の結果ならば和葉が阿呆でも別によいかのう」 雅音さんは捻くれた笑いを浮かべて車のドアを開けた。 「帰るぞ椿。いつまでも阿呆に付き合っておられん」 「はーい」 もう星弥も深散も大丈夫。今回のことで、心にあったわだかまりを解消できたから。 二人ともあんな風に心から笑っているのを見るのは初めてだから、心配ない。3人でぎゃーぎゃー騒いでる深散たちを一瞥して、私たちはその場を去った。 車の中で私はずっと疑問に思っていたことを雅音さんに尋ねた。 「ねぇ雅音さん」 「なんだ?」 「どうして雅音さんが紅葉さんを持ってたの?」 「ああ……」 雅音さんは忘れてたといわんばかりだ。 「今の賀茂に紅葉を返しても悪用はせんと判断したからだ」 「誰が?」 「俺がだ」 「………」 私が思わず黙ると雅音さんは私をちらりと横目で見ていった。 「何か物言いたげだのう」 「雅音さんって時々意味不明な権力働くよね」 「くくく。役に立つじゃろう」 「いや、うん。もちろんそれはね。でも……」 私は目を伏せた。 そして小さく言った。 「でも時々雅音さんが分からなくなる。一体何者なの?」 その呟きを雅音さんは聞き逃さなかったんだろう。 ぽんっと私の頭に手を乗せると、優しく撫でてくれた。 「俺は何者でもない。お前の婚約者、影井雅音だ。それでは不満か?」 不満なんかなかった。 でも、不安はあった。 雅音さん、どうして私に自分のことを一切話してくれないの? みんなは、雅音さんのことどこまで知ってるの? 「なんだか、私だけ雅音さんのことを何も知らないみたいで嫌」 拗ねたように言う私に雅音さんは突然車を止めた。 路肩に止まった車の中で、雅音さんは静かに私のほうを向く。 「何も知らん、か」 雅音さんは思わせぶりに笑った。 「それは大いなる勘違いじゃのう」 「え?」 雅音さんはふっと笑って私を胸に抱き寄せた。 「お前が一番本当の俺を知っておる。そうだろう?」 そう、優しく言われてしまうと首を横に振ることは出来ない。 確かに、きっと私はみんなに見せない雅音さんの顔を知ってる。 私だけに見せる、私だけがしってる雅音さんの甘い甘い表情。 ゆっくり唇を重ねられ、溶けていきそうな意識の中私はほんちょっとだけ祈った。 いつか雅音さんの全てを知ることができたらいいな、と。 |