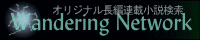第6話 振り返った先に
|
「よしよし、深散は頑張り屋でえらいなぁ」 「お父様、ありがとうー!」 幼いころの私は、みんなに褒められるうれしさを知っていた。 頑張れば、いい子にしていれば優しくしてもらえるから、私は必死にいい子になるための努力をしていた。 その対象は、お父様でありお母様であり、お手伝いさんであり、近所の人であり、友だちであり。 褒められれば誰でもよかった。 もちろんその中には、唯一血を分けた兄妹である、お兄様……賀茂和葉も例外なく入っていた。 けれどお兄様だけは、私を褒めてくれる周囲とは唯一違っていた。 誰もが、努力するいい子の私を建前であっても褒めてくれた。 でも、どんなにお兄様に私が努力したことを訴えても、お兄様は怪訝な顔で私を無視するだけだった。 お兄様は私を一度として褒めてくれたことはなかった。 「お兄様、お兄様見てみて! 今日は紅葉とお話しすることができたのよ!」 「………」 その日もお兄様は、周りの人たちが褒めてくれたことを一切褒めてくれなかった。 むしろ煩わしそうに顔を背けて、その場を去ろうとした。 だけれど、その日は流石に幼心に私も納得できなくてお兄様の手を取った。 「お兄様ったら! どうして何もいってくれないの!? みちる、式鬼神をちゃんと扱えたのよ!」 ずっと黙っていたお兄様も、その日ばかりはしつこい私に口を開いた。 それは別に褒め言葉でもなんでもない、私にとっては信じられない言葉だった。 「うるさい。うっとおしいから話しかけるな」 「え……?」 「式鬼神と話せたからって何だって言うんだ? そんなできて当然のことで話しかけるな!」 お兄様の言葉に、幼かった私は思わず泣き出した。 お兄様はそれにイライラしたのか、私を殴った。 流石に手を上げたことをお兄様は咎められ、良好とはいえなかった兄妹仲がますます悪くなってしまった。 お兄様は賀茂家の長男であり、次期当主の座が確定していた。 幸い賀茂家は、蘆屋家のようなお家争いもなく、本家の力がしっかり分家にも及んでいて有無を言わせない状態だった。 それはそうだろう。父である賀茂実鷹(かもさねたか)も、兄である賀茂和葉も、陰陽師としては申し分のない才能の持ち主。 母である賀茂散葉(かもちるは)も、優秀な陰陽師の家系から嫁いできたとなれば文句の言いようもないだろう。 特にお兄様は、お父様をも凌ぐ実力の持ち主と謳われる陰陽師。 将来を有望視された、私にとっても誇りに思える兄だった。 けれど、そんな尊敬するお兄様は私を一度として褒めてくれなかった。 それどころか、この17年生きてきた中で、一度として笑いかけてくれたことがない。 そしてあの日、初めてお兄様に手を上げられた日から、私とお兄様の間には大きな亀裂が生じてしまった。 いいえ……お兄様が私からさらに遠ざかった、といったほうが正しいかもしれません。 実際私はそれでもめげずにお兄様に努力の成果を報告して、その度に怪訝な顔をされて無視をされていた気がします。 何をすればお兄様が褒めてくれるのか、私はそれが知りたくてあらゆることを努力していた。 でも、いつになってもお兄様から褒められることはなく、私の考えはいつしか突拍子のないものになっていた。 「深散、今日はピアノの稽古の日だぞ。行かないのか?」 「もうあの教室にはいきませんわ」 ある日、私はピアノの稽古に行くことを拒んだ。 今まで、習い事を休んだことなど無かった私が絶対に行かないと言い張るものだから、お父様も驚いていた。 「どうしたのだ、お前らしくもない」 「だって、あそのこ先生では私これ以上上手くなれませんもの!」 多分、自分がお兄様に褒められない理由を、考えることを私は放棄していた。 自分が悪いわけがない、だとしたら教える側が悪いんだとひねくれた考えをするようになっていた。 思えばひどい言いがかりですわね…… でも、幼い私は、精一杯の努力をしているにも関わらず認められないのはおかしい、そう思ってしまっていた。 「そうか。ならば教室を変えてみようか。お前が納得いく先生を見つけなさい」 正直お父様は私に、甘すぎるほどに甘かった。 将来家を継がない私は、最低限の礼儀作法や陰陽師としての能力を持っていれば良しとされていた。 そしてそれが満たされていた私は、お父様にとってただ可愛がればいいだけの手のかからない娘だったに違いない。 私は、褒められることが好きだったから、親を怒らせるようなことをしたことがなかったのだから。 でも、逆にそれは私が自分は悪くないんだという意思を強める決定的な要素になっていたのではないかと今では思う。 ああ、これも自分の性格が歪んだのが親のせいである、なんていっていることになるのかしら。 決してそうじゃなくて、私はその環境に甘んじて我儘になっていった、ということ。 結局私はそれから、習い事を納得のいく先生が見つかるまでとことん変え続けた。 けれど、いくら実績を出してもお兄様は私に見向きもしなかった。 「お兄様、今日は絵画のコンテストで最優秀賞をとりましたのよ」 「……だから?」 「お兄様! 今日はお習字の階級が初段にあがりましたわ!」 「それがどうした?」 そんな無意味な問答の繰り返し。 私のイライラは頂点に達していた。 「もう! どうしてお兄様は私を認めないの!! 陰陽師としてだって、人としてだって、目に見える形でしっかり結果は出しているのに!!」 熊ぬいぐるみを床に叩きつけて癇癪を起こす私の肩を、紅葉は優しく撫でた。 「あまり怒るのはおよしになってください、深散様」 「紅葉……」 「きっと和葉様には和葉様のお思いがおありになるんですわ。それがいつかはお分かりになるときがきます」 「紅葉はお兄様が何を考えているか、分かるの?」 「なんとなく、分かるような気はします。けれど、これは生きていく中で深散様自身が見つけなくてはいけない答えであると私は思います」 「私自身が……見つける答え?」 「ええ、誰かに教えてもらったのでは絶対に分からないことだと思います」 私は紅葉の言っている意味が今でもあまり理解ができていない。 どんなに年月を重ねても、私がお兄様と理解しあえることはその後なかったのだから。 「え? 単身赴任?」 「ああ、関東にな、まだ陰陽師の力が及びきっていない地域があるのだ。そこで、陰陽師協会の新支部を作ることになってな。そこの支部長を務めることになったのだ」 「………」 私が小学校を卒業する年と共に出たその話に、私はお父様について京都を出ることを決意した。 きっと、別の場所で生活して別の生活をすればもっと自分を磨けると思ったからだ。 そこで必ずお兄様を見返してやる、私の思いはそんな方向へと進んでいた。 別に別れ難いと思う友だちもいなかった。 今思えば、私は本当の意味での友だちなんて椿たちが初めてなのかもしれない。 だって、今までの友だちは皆私の才能や財力を目当てに近づいてきただけ。私自身を見てくれた人なんて誰一人いなかったんだから。 そして住まうことになったのが星弥くんや椿たちに会ったあの町。 正直、都会ではない中途半端に田舎な町に私は驚いていた。 そこで、私は京都以上にひどい友人関係を築くことになる。 自分磨きのために習い事や勉強に努力をする日々、その私と友だちであることがステータスとでも思っているような子たちしか寄ってこないことに私は正直呆れていた。 転校してからも私は手紙でお兄様に手にした栄光の数々を報告したけれど、返事が帰ってくることは一度もなかった。 私のイライラは頂点に達していた。 「もう、なんですのよ! あの馬鹿お兄様!!」 私はそう言いながら道端の空き缶を蹴飛ばした。 「いで!」 カコーン! という音と共に、男の子の声が響いた。 蹴飛ばしたのはスチール缶だから、きっとぶつかりどころが悪かったらとても痛い。 私は慌てて缶をぶつけてしまった人のところに駆け寄った。 「大丈夫です!?」 「え? あー……これ、あんた……ってリボンの色からして先輩か……先輩が蹴ったんすか?」 「え、ええ……申し訳ありませんわ」 「ははっ、すげー勢いですっ飛んできたから、よっぽどイラついてたんっすね」 頭に缶をぶつけられたというのに、その男の子は怒ることもせずに笑うと、鞄から何かを取り出した。 「でもカルシウム不足は駄目っすよー! ほい、これ」 私の口に甘いミルク味が広がった。 それはミルクキャンディだった。 「これからは缶蹴飛ばすときは前方に注意してくださいねー!」 「あ! 待って!」 「んえ?」 「あ、あの……今度お詫びいたしますわ。お名前を教えていただけません?」 「あー、いいっすよお詫びなんて。でもそうっすね、これも何かの縁かもしれねぇっすね。俺は藤原星弥、本日よりこの学校に入学した1年っす。先輩は?」 「私は賀茂深散ですわ」 「賀茂先輩っすか! じゃあ、これからよろしくっす!」 そう、これが私と星弥くんの出会い。 私は星弥くんのあどけない笑顔にすぐに惹かれていった。 でも、彼と接していくうちに彼には既に思いを寄せる人がいることを知った。 「よっ! 椿―! 今帰りか?」 「うん、部活終わったからね。あんたは?」 「俺? 俺はダチとしゃべってて遅くなったんだ」 嘘。本当は椿を待っていたくせに…… まさか、もう日も落ちかけているような時間まで待ち続けるような人がいるなんて…… 私は絶望した。 あの女がいるせいで、星弥くんは私のほうをろくに見てくれない。 そう思ったら、無性に椿が憎くてたまらなくなった。 「………」 最初はちょっとした嫌がらせだった。 体操着を隠したり、上履きを隠したり。 でも、そんなことは気にも留めないような振る舞いの椿に私はイライラした。 まるで、私の努力を全く認めない、気にも留めない兄を見ているようだったからかもしれない。 そのせいか、私のいじわるはどんどんエスカレートしていった。 そして結局、今の親友を殺す寸前のことまでしてしまったのだから笑えない。 それどころか、愛する星弥くんに嫌われたくないがために、彼の生命の危機に晒してしまった。 その人の手を汚させてしまった。 「賀茂先輩、どういうことっすか!? 椿に、なんてことするんすか!!」 「藤原くん……! 私はあなたのことを思って……!!」 「俺のことを? ならなんで椿を危ない目にあわせたんっすか!!」 返す言葉がなかった。 責め立てられて、私の心はますます椿への憎しみに染まっていった。 「絶対に許さない……! あの女のせいで私は藤原くんに嫌われてしまった……!!」 今思えばひどい逆恨みだ。 私はお兄様に認められたいばっかりに目の前の成果を追い続けて、いつしか人間として大切な何かを失っていたように思う。 まさか、自分を見てもらうために人を殺してもいいなんて恐ろしいこと考えるなんて、どうかしていましたわ。 でも、その後私は後悔することになる。 星弥くんは茨木に精神の大半を浸食され、私には見向きもしなくなった。 それに失念していたことで、上辺だけの友だちの相手が億劫になって、私は一人でいることが多くなった。 そこで、我に返ってみれば私の周囲にはもう誰もいなかった。 そこで私は初めて自分の愚かさに気がついた。 私がしてきたことには何の意味もなかった。 得てきた数々の栄光は、愛する人を振り向かせる材料にはならなかった。 その栄光に釣られたのは、私を自らのステータスにしようとして近づいてきた上辺だけの取り巻きたち。 欲しいものは、私の努力では何一つ手に入らなかった。 おかしな話ね。 今まで血のにじむような努力で手にした栄光は私を少しも幸せにしてくれなかった。 なのに、散々意地悪をしてきた椿が私を許して友だちになってくれるといってくれた瞬間、賞状をもらって周囲に褒め称えられたときなんかより何十倍何百倍……いいえ、比べものにならないほど満たされた気持ちになった。 茨木に力を与えていたことに関して、家族は誰も私を責めなかった。 今まで、無理な努力を強いて、辛い思いをさせていたのだろうってなぜか両親はそういう方向に私の行動を捉えてしまったらしい。 私は取り繕う気はなかったものの、褒められるのが好きな私もそのときばかりは叱ってほしいと思っていた。 悪いことをしたら指摘して欲しかった。 私を止めて欲しかった。 褒めて認めるだけが愛じゃないって、椿たちと一緒にいることで気がついてしまったから。 私は、もしかしたら家族から見放されていたのかもしれない。 私を殴ったお兄様は、お父様に散々叱られていた。 でも、お兄様にしつこくしていた私は咎められたりしなかったのだから。 『そんなできて当然のことで話しかけるな!』 よく考えると胸に突き刺さる言葉ですわね。 確かに、いちいち報告するようなことでもなかったかもしれませんわ。 ん……? そうか、もしかしたらお兄様は…… 「深散? どうしたの?」 私は足を止めた。 影井様と一緒に帰ってきた椿と合流し、私たちは十六夜様に会いに蘆屋家に向かっていた。 「皆さん、ごめんなさい。私、本家に帰ろうと思います」 「いきなりどないしたん? おかんに会うの一番楽しみにしとったのミッチーやん」 「ええ、十六夜様には会いたいですわ。でも、今はどうしても本家に帰りたいんですの」 私の真剣な思いに最初に答えてくれたのは影井様だった。 「ふむ、賀茂家か。よいではないか、蘆屋家にはまた明日いけばよい。賀茂の表情を見ていると今すぐ行くべきなようだしの」 「影井様……ありがとうございますわ」 「なぁに、くくく。お前が何を思って今の状況で本家に帰ろうと考えたのか興味があるだけよ」 流石に影井様がオーケーを出したとあって、アッシーたちもしょうがないといったようだった。 私たちはすぐに賀茂家に向かった。 そこで私は久方ぶりのお兄様との再会を果たすことになる。 それがまさか、この事件解決の大きな鍵になるなんて、私は予想もしていなかった。 |